ブラウン神父の無心
このところ英語の本ばかり読んでいる気がするが、じつはそれらと並行して、日本語で書かれた一冊の本をかなり長いあいだ鞄に潜ませていた。仕事を早く切り上げられた日に、喫茶店へ直行して読むための本であり、短篇一篇あたりがだいたい、ちびちびと飲むコーヒー一杯分の時間で読み終えることができる(読み終えるころにはコーヒーは冷めているが)。それがあんまり楽しかったので、翻訳者違いの再読だというのに、初めて読むような興奮とともに最後のほうは心底惜しみつつ読み終えた。世界が求めていたコラボレーション、南條竹則訳の「ブラウン神父」。

- 作者: G.K.チェスタトン,G.K. Chesterton,南條竹則,坂本あおい
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2012/12
- メディア: 文庫
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
G・K・チェスタトン(南條竹則訳)『ブラウン神父の無心』ちくま文庫、2012年。
そう、あの『木曜日だった男』のときの最強タッグが、帰ってきたのだ! 2012年の刊行直後に慌てて買い、読む前から友人たちにこの価値を吹聴しまくっていたというのに、結局機会を見つけ出せないまま本棚で眠らせ続けていた一冊である。先日の「雑記:海外文学おすすめ作家ベスト100(2014年版)」を書いたことで、ようやく本棚を漁る気になったのだ(ところで、先日のケネス・グレーアムの『The Reluctant Dragon』もそうだったが、こういうきっかけを与えてくれるので、あの面倒なランキングを作るのもそう悪いことばかりではない)。最初の一篇を読むだけで、いや、その最初の一節を読むだけでも、わたしの判断(吹聴)はけっしてまちがっていなかったと確信した。南條竹則訳で「ブラウン神父」が読めるというのは、わたしにとっては『木曜日だった男』を読んで以来の、夢の実現だったのである。
「その様子からはとても察せられなかったが、灰色の上着の下には弾丸をこめた回転式拳銃がしのばせてあり、白いチョッキの下には警察の身分証、麦藁帽子の下にはヨーロッパ屈指の優れた知能が隠されていた」(「青い十字架」より、8ページ)
中村保男訳の創元推理文庫がいまでもいちばん手に取りやすいが、東京創元社はいい加減、文字を大きくするなりなんなりして、この傑作シリーズの価値をもっとアピールするべきだと思う。わたしも最初に読んだのはこの中村保男訳だったのだが、最初の一篇「青い十字架」を原文と照らし合わせて読んだときに、どの箇所だったかを思い出せないのが悔しいが、翻訳が省略されている箇所を見つけてしまったのだ。英語原文での読書に対する姿勢が大きく変わったいまとなっては、批判対象にすべきほどの省略だったのか確信が持てないものの、当時のわたしに不信感を募らせるには十分なことだった(だが、当時のわたしがチェスタトンを原文で読めたとも思えない。文字通り照らし合わせただけで原文を読んだ気になり、その際に偶然見つけた欠落、もしくはそれに近いものをねちねちと恨んでいたのにちがいない)。なんにせよ、訳文に対する信頼を失ってしまうと、それが正当なものであれ不当なものであれ、読書そのものが楽しめなくなってしまう。「南條竹則が訳してくれさえすれば……」と、そのときからずっとずっと願ってきたのだ。
「奇蹟というものの一番信じ難いところは、それが実際に起こることだ」(「青い十字架」より、13ページ)
「犯罪者は創造的な芸術家であり、刑事は批評家にすぎない」(「青い十字架」より、16ページ)
この「ブラウン神父」シリーズはコナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」シリーズと並んで、イギリスの探偵小説黄金時代を代表する作品群であるが、主人公のブラウン神父には、ホームズ的な意味でのいわゆる「名探偵らしさ」など、まったく見当たらない。頭のはげた小男、というのがブラウン神父に対して何度も繰り返される人物描写である。
「あの神父は、誰でも紐につないで北極まで引っ張って行けそうな男だ」(「青い十字架」より、29ページ)
「頭が馬鹿に大きい小さな人影が、月明かりの夜霧の中を、こちらへふわふわと近づいて来た。一瞬、小鬼(ゴブリン)のように見えたが、その正体は、三人が客間に残して来た人の良い小柄な神父だった」(「秘密の庭」より、51ページ)
彼はおおむね珍客としての立場で事件に居合わせ、一風変わった神父として周囲と接しているのだが、その意味深な言動は一風変わったどころではなく、完全に変人の域に達している。
「「そんなことを言うのは、やめて」娘が奇妙に頬を赫らめて、言った。「あなたがそんなことを言うようになったのは、あの恐ろしい何とかになってからよ。わたしの言ってる意味、わかるでしょう。煙突掃除人を抱きしめたがる人を何て言ったかしら?」
「聖者ですな」とブラウン神父が言った。
「わしが思うに」レオポルド爵士が人を見下したような微笑を浮かべて、言った。「ルビーが言っとるのは、社会主義者のことじゃよ」」(「飛ぶ星」より、114ページ)
「「眠るんだ!」とブラウン神父は言った。「眠るんだよ。我々は袋小路に入ってしまった。眠りとは何か、知っているかね? 眠る者はみな神を信じているのだということを知っているかね? 眠りは秘蹟なんだ。なぜなら、それは信仰の行為であり、糧であるからだ。そして、我々は自然の秘蹟でもいいから、秘蹟を必要としている。何か人間の身にめったに起きないことが、我々に起こったのだ。もしかすると、人の身に起こり得る最悪のことかもしれない」
クレイヴンの開いていた唇が閉じて、言った。「どういうことです?」
神父は城の方をふり向いて、こたえた。
「わたしたちは真実を発見した。しかし、その真実は意味をなさないということです」
神父は二人の先に立って、この人にしては珍しく、がむしゃらに突き進むような足取りで小径を下りて行った。城に帰り着くと寝床にさっさともぐり、犬のように他愛なく寝てしまった」(「イズレイル・ガウの信義」より、180~181ページ)
「「人は何度も笑うことが好きです」とブラウン神父はこたえた。「しかし、四六時中ニコニコしているのが好きだとは思いません。ユーモアのない陽気さというのは、じつに耐え難いものですからね」」(「三つの凶器」より、346ページ)
まったくもって、神父という立場が名探偵役に最適だと考えたのは、チェスタトンの数多の着想のなかでも最高の賞讃に値する思いつきだったろう。だが、ホームズやマーロウのような職業探偵が扱う事件には依頼人がいるものだが、ブラウン神父がその知性を発揮する対象はときとして探偵小説的な意味での「事件」ですらなく、その事実だけでもこの短篇集は、いわゆる探偵小説集とはまったく異なる様相を帯びている。
「その瞬間、神父は我を失っていたのだ。彼の頭脳はいつも我を失っている時こそ、真価を発揮した。そういう瞬間の彼は、二と二を足して四百万に出来るのだ」(「奇妙な足音」より、86ページ)
「神父は噂話を聞くのに何よりも大切な、好意ある沈黙のこつを心得ていて、自分はほとんど一言もしゃべらぬうちに、新しい知り合いから、かれらがいずれ話しそうなことを全部聞いてしまうのだった」(「サラディン公の罪」より、229ページ)
「「いいですか、先生」神父は愛想良く微笑んで、こたえた。「わたしのような職にあるものは、物事に確信がない時は胸にしまっておきますが、それにはもっともな理由がありましてね。というのは、確信がある時も、常に胸にしまっておくのが義務だからです」」(「神の鉄槌」より、272ページ)
そしてブラウン神父の明晰な頭脳は、たいてい驚くべき論理を展開して読者の度肝を抜いてくる。チェスタトンの「トリック創案率」(いかにも探偵小説の用語だ)は随一、という、江戸川乱歩の有名な言葉も頷ける。
「人はふつうコーヒーに塩が入っていたら、少しは騒ぐものです。もし騒がないなら、黙っている理由があるんです。わたしは塩と砂糖をすり替えましたが、あなたは黙っていました。人はふつう勘定が三倍も高かったら、文句を言うでしょう。おとなしく払ったとすると、目立ちたくない動機があるんです。わたしは勘定書を書き変え、あなたはそれを払った」(「青い十字架」より、38ページ)
「「君も妙だと言い、わたしも妙だと言う」と神父は言った。「ところが、二人は正反対のことを言わんとしているんだ。現代人はつねに二つの異なった概念を混同する――驚嘆すべきことという意味の不思議と、複雑なことという意味の不思議をだ。奇蹟というものの厄介さは、半分がそこにある。奇蹟は驚くべきものだが、単純だ。奇蹟であるが故に単純なのだ。それは自然や人間の意志を通じて間接にやって来るものではなく、神(あるいは悪魔)から直接来る力なのだ。ところで、君はこの事件を奇蹟的だから、邪悪なインド人のあやつる魔法だから、驚嘆すべきだと言う。いいかね、わたしはこの事件が霊的でも悪魔的でもなかったと言うわけじゃない。人を取り巻くいかなる影響力によって、人間の生活に奇妙な罪が生まれるかを知っているのは、天国と地獄のみだからね。しかし今、わたしが言いたいのはこういうことだ――もしこれが君の考えるように純然たる魔術だとすれば、それは驚異だが、不思議ではない――すなわち、複雑ではないということだ。奇蹟は性質としては不思議だが、起こり方はいたって単純だ。そして、今回の事件の起こり方は、単純とは正反対だった」」(「間違った形」より、211~212ページ)
ちなみに以下の箇所は、小笠原豊樹も『マヤコフスキー事件』のなかで引用していた。
「ねえ、お気づきになったことはありませんか――人はこちらの言うことには、けっしてこたえないのに。人はこちらの意味することに対して――あるいは、かれらがそう受けとったことに対してこたえるのです。仮に田舎のお屋敷で、ある御婦人がべつの御婦人に「お宅にどなたか御滞在ですか」とたずねたとします。相手は「はい。執事と三人の従僕と、部屋付きの女中などがおります」とは言わないでしょう。その部屋には女中が控えていて、椅子のうしろに執事が立っていたとしてもです。その婦人は、相手が言うような人間はいないという意味で、「誰もおりません」とこたえるでしょう。しかし、仮に伝染病の調査をしている医者が「お宅にはどなたがおられますか?」とたずねたら、その時は、くだんの婦人も執事や女中のことを思い出すはずです。言葉はすべてこんな風に使われるもので、質問に対する文字通りの答は返って来ないのです。たとえ正しい答が返って来るとしてもね」(「透明人間」より、158ページ)
この作品集はわたしに言わせればぜんぜん探偵小説らしくなく、そのような一ジャンルで括るという矮小化を許すようなものではない。これが文学でなかったらいったいなにが文学なのだ、と言いたくなるような文章が随所に散りばめられているのだ。
「「真の漁師十二人会」が年に一度の晩餐会を開いたヴァーノン・ホテルは、行儀作法に拘泥してほとんど狂気の域に達した寡頭政治社会でなければ、存在し得ないような施設だった。それはあの逆転の産物――「排他的」な営利事業だった。すなわち、人を引きつけるのではなく、文字通り追い払うことによって金を儲ける商売だったのである。金権社会の中心地では商人も賢くなり、お客以上に選り好みすることをおぼえる。かれらはわざと難しい障碍を設け、退屈した金持ちの顧客がその難関を突破するために、金と術策を用いるように仕向ける。もしもロンドンに、身長六フィート以下の者は入れないという流行のホテルがあったら、社交界は文句も言わずに六フィート以上の人間を集めて、晩餐会を開くだろう。また、もしも経営者のただの気まぐれから、木曜日の午後にしか店を開けない高級レストランがあったら、木曜の午後は大繁盛するだろう」(「奇妙な足音」より、77ページ)
「「真の漁師十二人会」の晩餐は、最初の二品まで滞りなく終わった。筆者はこの時のメニューを持っていないが、もし持っていたとしても、誰にも珍文漢文だったろう。それは料理人が用いる一種の超絶フランス語で書いてあったが、フランス人が見てもさっぱり理解出来ぬ代物だった」(「奇妙な足音」より、88ページ)
「森の千本の腕は灰色で、百万の指は銀色だった。濃い青緑がかった石瓦色の空には、星が氷のかけらのように寒々しく燦めいていた」(「折れた剣の招牌」より、310ページ)
それぞれの作品ごとの登場人物たちも、一風変わっている。いや、ほかの探偵小説にも出てくるような影の薄い、普通の人びとだったのかもしれないが、チェスタトンによって描かれるということは、彼らを平凡とはおよそ縁遠い、印象的な人びとに変貌させるということなのだ。
「彼の道楽の一つは、アメリカにシェイクスピアが現われるのを待つことだった――釣りよりも気長な趣味といえる」(「秘密の庭」より、45ページ)
「副会長のチェスター公爵は、新進の青年政治家だった。というのはつまり、ぺったりと撫でつけた金髪に雀斑(そばかす)だらけの顔をした感じの良い若者で、ほどほどの知性と莫大な資産の持主だったということである。公の場に出ると、彼の風貌は常に人気を博し、主義主張は単純明快だった。冗談を思いつけばすぐ口に出して、才気煥発だと評判された。冗談を思いつかない時には、今はふざけている場合ではないと言って、有能だと評判された」(「奇妙な足音」より、89ページ)
「上等のコーヒーとリキュールで昼食が終わりになると、客人たちは庭と書斎を案内され、女中頭に紹介された――女中頭は肌の浅黒い、顔立ちのととのった女性で、中々の威厳があり、さながら冥界の聖母という風だった」(「サラディン公の罪」より、228ページ)
冥界の聖母ってなんだよ! と叫びだしたくなってしまう。ほかにもまだまだたくさんある。
「ウィルフレッド・ブーン師はたいそう信心深く、暁の祈りか瞑想の厳しいお勤めに行くところだった。兄のノーマン・ブーン大佐は信心深いとはとても言えず、夜会服を着て「青猪亭」の軒先の腰掛に坐り、酒を飲んでいたところだったが、この酒を火曜日の最後の一杯と見なすのも、水曜日の最初の一杯と見なすのも、哲学的な観察者の自由であった。大佐は細かいことを気にしなかった」(「神の鉄槌」より、252ページ)
「靴屋はどの村でも大抵そうだが、無神論者で、この男が教会に現われるのは、「瘋癲ジョー」が現われるよりもさらに異常な事態だった。まことに、この日の朝は神学上の謎に満ちていた」(「神の鉄槌」より、258ページ)
「もっと清教徒色の強い演壇や説教壇では、今や定番となった改宗話をよくやった。まだほんの少年の頃、スコットランドの神学からスコットランドのウイスキーに心が移り、やがてその双方と訣別して、現在の自分(と彼は謙虚に言った)があるという話である」(「三つの凶器」より、340~341ページ)
なかでも「アポロンの目」の主要人物であるポーリーン女史の人柄はとくに忘れがたく、ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』にも描かれていたフェミニズムと機械文明との強固なつながりを意識せずにはいられなくなる。
「彼女は現代的職業婦人であり、現代的な作業機械を愛するということだった。輝く黒い瞳は、機械科学を非難し、ロマンスの復興を求める連中への観念的な怒りに燃えていた。自分がこうしてエレベーターを操るように、万人が機械を操れるようにならなければいけないと言うのだった。彼女はフランボーがエレベーターの扉を開けてやったことにさえ、腹を立てているらしかった」(「アポロンの目」より、286ページ)
「バッテリーやモーターといったものは、人間の力の象徴です――そうですわ、フランボーさん、それに女の力の象徴でもあります! 今度はわたしたちが、距離を縮め、時間に挑む偉大な機関を使う番です。それは高尚で素晴らしいものです――本当の科学ですわ」(「アポロンの目」より、287ページ)
こういった登場人物たちが交わすなにげない会話も大変気が利いていて、まったくもって、読んでいてこれほど楽しい本はない。
「略奪を是とするような意見といい、可愛い名づけ子と親密そうな様子といい、フィッシャーには赤ネクタイの青年が気に入らなかったので、思いきり嫌味を利かせて、横柄に言った。「さだめし君は、シルクハットに坐るよりも、うんと下品なことを知っておるんだろうね。それは一体、どんなことかね?」
「シルクハットが頭の上に坐ってることですよ。たとえばね」と社会主義者は言った」(「飛ぶ星」より、117ページ)
「「なんてことかしら。わたし、気が変になってしまったのよ」
「本当に狂ってるなら」と青年は言った。「正気だと思うだろうよ」」(「透明人間」より、143ページ)
複数作品にまたがって登場する、ブラウン神父以外のもう一人の主要人物、フランボーについては、理由があって多くを書くことはできない。ただ、その理由というのは実際にこの本を手にとってもらえばすぐに理解できることだし、ことこの本に関して言えば、彼の名前をここに記したところで読書の楽しみが減るなんてことは絶対にありえないので、引用してしまおう。
「「心理学が何だか知らないのかい?」フランボーが親しげに驚きを示して言った。「心理学っていうのは、オツムがイカレることさ」」(「イズレイル・ガウの信義」より、168ページ)
「船は二人なら何とか快適に乗れるだけの広さで、どうしても必要な物しか載せることが出来ず、フランボーは彼一流の哲学で必要と思われるものを積み込んだ。それは結局、四つの必需品に帰着したとおぼしい。腹が減った時のための鮭の缶詰、闘いたい時のための弾を塡めた回転式拳銃(リヴォルヴァー)、失神した時のためらしきブランデー、それに神父が一人――これは死んだ時のためと思われる」(「サラディン公の罪」より、222ページ)
ブラウン神父とフランボーの会話にも、すばらしいものがたくさんある。フランボーはブラウン神父の「世界でたった一人の友達」なのだ。
「あそこのベランダの下に長い腰掛がある。あそこなら、雨に濡れないで一服できるだろう。君は世界でたった一人の友達だから、話がしたいんだ。というよりも、一緒に黙っていたいのかもしれんな」(「間違った形」より、211ページ)
「「おれが聞いたところでは」とフランボーはこたえた。「人間は心が一徹ならば、どんなことにも耐えられるというのが、連中の理論なんだそうですよ。あのお宗旨の二つの大きな象徴は、太陽と見開いた目でしてね。というのも、人が本当に健康なら、太陽を見つめられると言ってるんです」
「人が本当に健康なら」とブラウン神父が言った。「太陽を見つめようなんて気は起こすまいよ」
「まあ、あの新宗教についておれに言えるのは、それだけです」フランボーは気楽に語り続けた。「もちろん、身体のどんな病気も治せると言ってます」
「魂のただ一つの病を治せるかね?」ブラウン神父は、本気で好奇心をそそられたように訊ねた。
「魂のただ一つの病って、何です?」フランボーはにやにやして聞き返した。
「自分がまったく健康だと考えることさ」と彼の友人は言った」(「アポロンの目」より、283~284ページ)
「「君の話はきれいな話だ」ブラウン神父は深く感じ入ったように、言った。「素直で、純粋で、正直な物語だ。あの月のように開け放しで真っ白だ。狂気と絶望にはまだ罪がない。世の中にはもっと悪いものがあるんだよ、フランボー」」(「折れた剣の招牌」より、320ページ)
ブラウン神父は神父なので、神学的な話も多少はあるのだが、彼のそれは神学というよりも哲学に近く、信仰のないわれわれに理解できないようなものではない。いま、哲学と書いてみて、とてもしっくりきた。こんなに哲学的な探偵小説はない。これほど自然に哲学を織り交ぜた文学作品はそうそうないだろう。
「間違った哲学でも、この宇宙にあてはまるものが十はある。間違った説でも、グレンガイル城にあてはまるものが十はある。だが、我々が求めているのは城と宇宙の本当の説明です」(「イズレイル・ガウの信義」より、173ページ)
「本物の宗教にはすべて、一つの特徴がある――唯物主義だ。だから、悪魔崇拝も立派に本物の宗教といえるのだ」(「イズレイル・ガウの信義」より、177ページ)
「「わたしは人間です」ブラウン神父は真面目にこたえた。「それ故に、心の中にあらゆる悪魔を持っています」」(「神の鉄槌」より、278ページ)
「人は一体、いつになったら理解するんだろう――他のすべての人間の聖書も読むのでなければ、自分の聖書を読んだって無益だということを」(「折れた剣の招牌」より、330ページ)
この本の解説は残念ながら南條竹則によるものではないが、バーナード・ショーとの友情の話など、おもしろいエピソードがたくさん語られていて、とても楽しかった。ウェルズの『盗まれた細菌/初めての飛行機』を紹介したときにも大変興味をそそられた彼らの関係については、なにかまとまった本を読んでみたいと思っている。ひょっとしたらマックス・ビアボウムがなにか書いているかもしれない。
「チェスタトンの巨軀(なんと身長一メートル九三センチ、体重は一三〇キロ!)にまつわる逸話は数多いが、前述のショーとのやり取りは特に面白い。痩身の菜食主義者ショーをチェスタトンが「君を見たら、誰だって、イギリスは飢饉に襲われたと考えるぞ」とからかうと、ショーはこう答えた。「君を見たら、誰だって、飢饉の原因が君だって考えるだろうね」」(高沢治「解説」より、370ページ)
チェスタトンは圧倒的である。これをおもしろいと思わないひとには、もう薦められる本などない。『無心』は五冊刊行された作品集のうちの一冊目でしかないので、まずは二巻目にあたる『The Wisdom of Father Brown』(中村保男の訳題では『ブラウン神父の知恵』)の刊行を心待ちにしたい。ほんとうに、読み終えたくなかった。

- 作者: G.K.チェスタトン,G.K. Chesterton,南條竹則,坂本あおい
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2012/12
- メディア: 文庫
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
〈読みたくなった本〉
コールリッジ『老水夫行』
「外では、コールリッジの詩の夜のごとく嵐が一足にやって来て、庭もガラス屋根も激しい雨に打たれ、暗くなって来た」(「間違った形」より、206ページ)
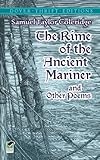
The Rime of the Ancient Mariner (Dover Thrift Editions)
- 作者: Samuel Taylor Coleridge,Dover Thrift Editions
- 出版社/メーカー: Dover Publications
- 発売日: 1992/09/18
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
ニーチェ『道徳の系譜』
「カロンと名乗る男は堂々たる美丈夫で、風貌からすれば、アポロンの大祭司にふさわしかった。フランボーにも負けないほどの上背があり、はるかに男前で金色の顎鬚を生やし、凛とした青い瞳をして、髪を獅子の鬣(たてがみ)のようにうしろへ流していた。肉体はまさにニーチェのいう金毛獣そのものだったが、こうした動物的な美しさが真の知性と霊性によって高められ、輝きを増し、和らげられていた」(「アポロンの目」より、288ページ)

- 作者: フリードリヒニーチェ,Friedrich Nietzsche,中山元
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2009/06/11
- メディア: 文庫
- 購入: 8人 クリック: 25回
- この商品を含むブログ (23件) を見る