雑記:海外文学おすすめ作家ベスト100(2014年版)
2011年を最後に更新していなかった、いわゆる「好きな作家ベスト100」を掲載する。公開した途端に後悔する、という、あれである。名前が「好きな作家ベスト100」でなくなったのは、「好きな」というのと「ベスト」というのが、同じことを意味していることに気づいたからだ(遅い)。「おすすめ」と銘打ってはいるものの、玄人ぶるつもりはないが、だれが読んでもおもしろいというような作家ばかりではない。また、例年どおり、順位はそのときの気分次第なので、あまり深く考えないでいただきたい。1位から20位くらいまでは全員1位、20位から50位くらいまでは全員2位、50位以下は全員3位という感覚だ。
以前は1位から順に発表という、緊張感もなにもないリストだったのだが、今回はこの「はてなブログ」に引っ越してからの初めての公開ということで、「見出し」機能を大いに駆使し、緊張感抜群の形式を実現した(※個人の感想です)。50位以下でもおもしろい本ばかりなので、なるべくそれを伝えようと、言葉を費やしている。とてつもなく長大なリストではあるが、「こいつ、いつもどおり面倒くせえな」と思われた方は、見出しだけさくさくとスクロールされるのがよろしいだろう。
ほとんどすべての作家に、その作品を紹介した記事へのリンクが貼ってあるので、あわせてそちらも参照されたい。また、書影を掲載した書籍は特に読んでもらいたいもの。それではベスト100のはじまりはじまり。
100.ラッタウット・ラープチャルーンサップ
Rattawut Lapcharoensap(1979-)
『観光』(Sightseeing, 2005)

- 作者: ラッタウットラープチャルーンサップ,Rattawut Lapcharoensap,古屋美登里
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2010/08/30
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 59回
- この商品を含むブログ (23件) を見る
記念すべき第100位はラッタウット君である。先に言ってしまうが、彼はこのランキングに名を連ねた作家のなかで最も若い。というか、存命の作家がほとんどいないなかでの、まさかの1979年生まれという快挙である。この本には物語の外側にいくつものすばらしい思い出があって、それが背中を押し、2011年のときと同様の100位となった。いや外せないよ、ラッタウット君は。とはいえ小説もすばらしいものなので、とくに村上春樹の短篇が好きな人にはぜひ読んでみてもらいたい。ちなみにタイ人。
「セックスと象だよ。あの人たちが求めているのはね」(「ガイジン」より、『観光』9ページ)
099.エマニュエル・ボーヴ
Emmanuel Bove(1989-1945)
『ぼくのともだち』(Mes amis, 1924)、『きみのいもうと』(Armand, 1927)
『ぼくのともだち』は疑いようもない傑作なのだが、続編である『きみのいもうと』は、残念ながら満足させてくれるものではなかった。ジャン=フィリップ・トゥーサンの『浴室』や『ためらい』、ヴィレム・エルスホットの『9990個のチーズ』を思わせる気だるい世界観には、たまに立ち戻りたくなる。あまり翻訳されていないが、原書を探してまで読もうとは思わない。
「洗面を済ますと気分がよい。鼻で息を吸ってみる。歯の輪郭が一本一本はっきり感じられる。手のひらも昼ごろまでは白いままだろう」(『ぼくのともだち』10ページ)
098.ダイ・シージエ
Dai Sijie(1954-)
『バルザックと小さな中国のお針子』(Balzac et la petite tailleuse chinoise, 2000)、『フロイトの弟子と旅する長椅子』(Le Complexe de Di, 2003)
『バルザックと小さな中国のお針子』があまりにもすばらしい本だったので、喜び勇んで『フロイトの弟子と旅する長椅子』を読み、大変がっかりさせられた記憶のある作家。それ以来、新たに翻訳された『月が昇らなかった夜に』や『孔子の空中曲芸』にも手を出していない。『夜想曲集』のときのカズオ・イシグロなどと同様、たまに自分に酔っているような印象を与えることがあり、読んでいるこちらとしては白けてしまうのだ。それでも『バルザックと小さな中国のお針子』のすばらしさは忘れられない。
097.アゴタ・クリストフ
Agota Kristof(1935-2011)
『悪童日記』(Le Grand Cahier, 1986)、『ふたりの証拠』(La Preuve, 1988)、『第三の嘘』(Le Troisième Mensonge, 1991)、『昨日』(Hier, 1995)、『文盲』(L'Analphabète, 2004)、『どちらでもいい』(C'est égal, 2005)

- 作者: アゴタクリストフ,Agota Kristof,堀茂樹
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2001/05
- メディア: 文庫
- 購入: 100人 クリック: 3,630回
- この商品を含むブログ (267件) を見る
昔は好きだったけれどいまは愛を公言するのがためらわれる、という現象は、なにもアイドルグループに対してのみ起こる話ではない。アゴタ・クリストフに対するわたしの感情はまさしくそれで、『悪童日記』がとんでもなく好きだったからこそ、その後の彼女の書くものには不満を抱くばかりだった。自伝的な『文盲』は例外的におもしろいが、『昨日』や『どちらでもいい』などははっきりと駄作で、自己啓発書でも読まされているような嫌な気分になる。さらに言えば、三部作二作目の『ふたりの証拠』、三作目の『第三の嘘』からしてすでに、第一作の『悪童日記』の衝撃は到底超えられていないのだった。とはいえ『悪童日記』は、やはり何度読んでもすばらしい。クンデラと並んで、亡命という現代のオデュッセウスたちの物語を語らせたら、右に出るものはいない作家である。
「当時のわたしは、別の言語が存在し得るとは、ひとりの人間がわたしには意味不明の単語を口にすることがあり得るとは、想像することもできなかった」(『文盲』38ページ)
096.ヤスミナ・カドラ
Yasmina Khadra(1955-)
『カブールの燕たち』(Les Hirondelles de Kaboul, 2002)、『テロル』(L'Attentat, 2005)、『昼が夜に負うもの』(Ce que le jour doit à la nuit, 2008)
こんな日常がありえるのか、こんな暴力がまかりとおるのか、と、息を呑みながらページを繰ること必至の作家。『昼が夜に負うもの』は、なかでもいちばんのおすすめで、現代のアルジェリアに関心のある方には必読書と言ってもいいだろう。ブルース・チャトウィンの『どうして僕はこんなところに』でもすこしだけ語られているが、アルジェリア戦争をいつまでも「戦争」と呼ばなかった宗主国フランスは、われわれの想像を絶することをいくつもしており、そのことを教えてくれる本はまだけっして多くはないのである。ただ、この作家はなにもかもメロドラマ風にしたがる傾向があり、来日した本人に会うまではあまり気にしていなかったのだが、自作の売れ行きを大変気にしていたり、スター扱いされるのが大好きと、小物感がつきまとう。今年(2014年)もわたしがいま住んでいる国で講演をしていたのだが、やはり売れ行きや知名度ばかり気にしていたという。
「アルジェリア人のアルジェリアは、涙と血の増水のなかで鉗子分娩によって生まれようとしていた。フランス人のアルジェリアは、滝のような瀉血のなかで命を終えようとしていた」(『昼が夜に負うもの』405ページ)
095.アンドレイ・クルコフ
Andrey Kurkov(Andreï Kourkov)(1961-)
『ペンギンの憂鬱』(Смерть постороннего, 1996)

- 作者: アンドレイ・クルコフ,沼野恭子
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2004/09/29
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 2人 クリック: 68回
- この商品を含むブログ (159件) を見る
アンドレイ・クルコフの楽しさは忘れがたい。『ペンギンの憂鬱』一冊を読んだきりで、もうひとつの訳書である『大統領の最後の恋』にはいつまでも手を出せずにいるのだが、読めば満足させてくれるであろうことは疑いない。『ペンギンの憂鬱』は以前、「2007年に読んでもっともおもしろかった本」に選出した。けっして長篇小説を書けない短篇作家である主人公のペット、憂鬱症を患ったペンギンが、直立不動でうなだれている話である。英語やフランス語にはたくさん翻訳されている、現代ウクライナを代表する作家。
094.ブノワ・デュトゥールトゥル
Benoît Duteurtre(1960-)
『幼女と煙草』(La Petite Fille et la Cigarette, 2005)

- 作者: ブノワ・デュトゥールトゥル,赤星絵里
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2009/10/09
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 139回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
日本ではまだ『幼女と煙草』しか翻訳が出ていないが(※)、フランスでは小説作品だけでもう20作も発表している、そこそこ有名な作家である。まだ感想は書いていないものの、『Service Clientèle』という一発ギャグのようなごく薄い長篇作品を読んだことがあり、げらげら笑った記憶がある。電話の自動返答システム相手に延々と格闘する、という話である。フランスでも日本でも、もっと認められてもよさそうな作家。『幼女と煙草』はとくに、ユゴーの『死刑囚最後の日』とあわせて読むと楽しいかもしれない。
※追記(2015年1月4日):昨年4月にメディシス賞受賞作『フランス紀行』(Le Voyage en France, 2001)が翻訳されていました。しかも西永良成氏によって! もと(@nn0to)さん、ご指摘ありがとうございました。
「大人の権利のうち一番のものは、まぎれもなく“喫煙”だった……。ガンになるリスクなんてどうでもよかった。それどころか、映画や広告はこの習慣を、自由を表わす行為と見るよう僕らに教えてくれた。煙草に火をつける、口にくわえる、煙を吐く。この変わった芸当は、それを行なう人間にモダンで洗練されたエレガントな物腰を与えていた。役立たずで、観賞用とも言える物、煙草は、人間を動物と分けていたのである」(『幼女と煙草』53ページ)
093.チャールズ・ブコウスキー
Charles Bukowski(1920-1994)
『ポスト・オフィス』(Post Office, 1971)、『町でいちばんの美女』(The Most Beautiful Woman in Town & Other Stories, 1983)、『パルプ』(Pulp, 1994)

- 作者: チャールズブコウスキー,Charles Bukowski,柴田元幸
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2000/03
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 30回
- この商品を含むブログ (48件) を見る
ブコウスキーというのはおかしな作家で、妙な中毒性があり、読んでいる最中は「もう二度とこの作家の本は手に取らない」なんて思うのだけれど、しばらく時間を置くと、どういうわけかまた手に取っている。英語圏では小説と並んで詩が人気で、いわゆる「ビート」の作家たちにいかれた若者たちが、こぞって彼の詩集を読んでいるイメージがある。大丈夫か、アメリカ。セリーヌとの親和性は抜群。ちなみに『町でいちばんの美女』の表紙の女がぜんぜん美女じゃないのは、たぶん日本オリジナルの気の利いた仕様。
「ベイビー。そんなの小学生だってできるぜ。どんなうすのろだって仕事くらいありつけるんだよ。本当に賢い人間っていうのはな、働かずに暮らしていける奴のことなんだ。内輪の言葉じゃ“博徒(ハスラー)”って言うんだけどな。俺はカッコいいハスラーになりたいね」(『ポスト・オフィス』87ページ)
092.アンリ・バルビュス
Henri Barbusse(1873-1935)
『地獄』(L'Enfer, 1907)
『地獄』の一冊しか読んだことがないのだが、意外なことに翻訳はかなり出ていて、以前は日本でも名の知られた作家だったことがわかる。わたしがこの作家を知ったのも、向田邦子のエッセイ『父の詫び状』が教えてくれたおかげである。「のぞき文学」というジャンルがあるとしたら『地獄』はその筆頭であり、前半の背徳感は、じつは読書という行為自体が作中人物たちに対する「のぞき」なのでは、という感覚と相俟って、ものすごい緊張感を帯びる。中盤くらいからは話が呪詛の塊のようになっていき、セリーヌでも読んでいるような嫌な気分で読み進めることになるのだが、前半の方が圧倒的におもしろい。癌の絞り汁から上質のシャンパンが作れる、という情報は、この本で得た収穫。
「夢はいつもわしらを苦しめるものだ。悲しい夢はわしらの夜を台なしにし、楽しい夢はわしらの昼を傷つける」(『地獄』152ページ)
091.E・T・A・ホフマン
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann(1776-1822)
『ホフマン短篇集』(編纂)

- 作者: ホフマン,E.T.A. Hoffmann,池内紀
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1984/09/17
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
ホフマンはブコウスキーと同様、と書くと妙な語弊があるが、不思議な中毒性を持った作家である。じつはまだ感想を書いていないだけで、『クルミわりとネズミの王さま』や『黄金の壺/マドモワゼル・ド・スキュデリ』も読んでいるのだが、なにも考えずに物語に身を委ねられる気やすさは、なにものにも代えがたい。そういう意味では最近熱心に読んでいるブルガーコフにも、ホフマンと通じるところがあるように思える。『水妖記』のフーケや『影をなくした男』のシャミッソー、『ミヒャエル・コールハースの運命』のクライストは、今回のリストには含めなかったが、「ドイツロマン派」と一括りにされることの多い彼らを代表させるには、ホフマンはうってつけだ。
「読書好きの花売り娘とくれば物書きにとって、とてもじゃないがたまらない見物じゃないか」(「隅の窓」より、『ホフマン短篇集』286ページ)
090.ロバート・キャパ
Robert Capa(1913-1954)
『ちょっとピンぼけ』(Slightly Out of Focus, 1947)
キャパは写真家として有名だが、じつはものすごく文章がうまい。そのことを高らかに告げるのが彼の回想記、『ちょっとピンぼけ』である。初めに読んだのは友人が貸してくれたもので、返したくなかったので新しいものを途中で買ったのだが、新しい本をその友人に返そうとしたら、「家に2冊あるからあげるよ」と言われた。その後、どこだったか出先で無性に読みたくなり、家に2冊もあるとわかっているのに、また新しく買ってしまった。だからこの本はいま、日本の実家の本棚に3冊も並んでいる(ちなみにもっとも多いのは太宰治の『走れメロス』新潮文庫版。これほど出先で急に読みたくなる本はないのだ。5冊もある)。最初に紹介してくれた友人の趣味同様、ハードボイルドと親和性が高い。チャンドラーやヘミングウェイ、ダシール・ハメットやロス・マクドナルドが好きな人にはとくに手にとってもらいたい。
「私のカメラのファインダーのなかの数千の顔、顔、顔はだんだんぼやけていって、そのファインダーは私の涙で濡れ放題になった」(『ちょっとピンぼけ』181ページ)
089.ウィリアム・トレヴァー
William Trevor(1928-)
『聖母の贈り物』(編纂)

- 作者: ウィリアムトレヴァー,William Trevor,栩木伸明
- 出版社/メーカー: 国書刊行会
- 発売日: 2007/02
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 29回
- この商品を含むブログ (37件) を見る
ぜんぜん関係ないのに、トレヴァーはわたしにとって、パリを思わせる作家だ。プルースト以外の本を持たないと決めてフランスに向かったわたしの唯一の例外が、まだ読みかけだったために機内持ち込みしたこの短篇集だったのだ。もちろん、「読書=プルースト」というのは大変息のつまるものである。読み終えたのは当時住んでいた家の隣にあったカフェで、最後のほうはもったいない気持ちから、それはもうちびちびと読んでいた。チェーホフや、チェーホフを範としたロジェ・グルニエのように、登場人物との距離感が際立った短篇を書く作家で、ご存命、きっといまでも書いていらっしゃる。そういえば2011年にロンドンのチャリング・クロス街の古本屋で、「ウィリアム・トレヴァー、83歳の誕生日おめでとう」という札とともに、二冊の初版本が並べられていたのを見たことがある。とても買える金額ではなかったが、無理をしてでも買えばよかった、と、いまになって思う。
「嘆きの万華鏡の内部で真っ赤な血が爆発したかのように、彼女の意識の内側をまぶしくて激しいさまざまな色が駆けめぐった」(「雨上がり」より、『聖母の贈り物』392ページ)
088.ゴールドストーン夫妻
Lawrence & Nancy Goldstone
『古書店めぐりは夫婦で』(Used and Rare, 1997)、『旅に出ても古書店めぐり』(Slightly Chipped, 1999)

- 作者: ローレンスゴールドストーン,ナンシーゴールドストーン,Lawrence Goldstone,Nancy Goldstone,浅倉久志
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 1999/09
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 18回
- この商品を含むブログ (17件) を見る
本好きのための本、というと、まず最初に思い浮かぶのが彼らの『古書店めぐりは夫婦で』だ。これはお互いの誕生日が近い夫婦が、双方へのプレゼントにかける金額を抑えるルールを設け、妻のほうが古本屋で規定金額内の図板入『戦争と平和』を見つける、というところから話がはじまるエッセイである。彼らは古書の世界の広大さに取り憑かれ、愛するあらゆる作品の豪華装幀版を買い集めるようになるのだ。手持ちがあればいつも本を買ってしまうようなひとにはうってつけの本で、この本を片手に神保町なんかをうろうろしていたら、破産することは確実だ。古書を題材にしたエッセイではヘレーン・ハンフの『チャリング・クロス街84番地』が有名だが、著者の趣味が自分と合っていないので、こちらのほうが圧倒的におもしろい。アン・ファディマンの『本の愉しみ、書棚の悩み』もあわせて読んでみてもらいたい。
087.アール・ラヴレイス
Earl Lovelace(1935-)
『ドラゴンは踊れない』(The Dragon Can't Dance, 1979)
セリーヌが好きだということを公言する物騒な友人が薦めてくれた本で、彼のようなひとに薦められなかったら耳にすることもなかったであろう、トリニダード・トバゴの作家。カリブ海、というか中南米の人びとにとって、年に一度のお祭りがどんなに重要なものであるかを、これほど雄弁に物語った小説はないだろう。翻訳もすばらしいもので、もともと日本語で書かれたみたいにすらすら読める。英語の原書ではかなりの冊数が刊行されているので、もっとたくさんの翻訳が出ても良さそうなものだ。セリーヌのように反骨精神に溢れてはいるけれど、ディケンズのように物語を紡ぐこともけっして忘れない作家。
「フィロ自身があのターザンのカリプソでいいたかったこと、それはもしターザンが本当にいたならアフリカ人は彼を食っていただろうということだった。アフリカ人が人食い人種であるという考えは気にいった。そりゃもうわくわくするような、とんでもなくいけない光景だっただろうな! ターザンがでっかい湯気の立った鉄鍋に入れられて、周りをアフリカ人が飛び跳ねてやつが煮えるのを待ってるんだ。あの歌を聴くたび、彼は笑った」(『ドラゴンは踊れない』302ページ)
086.ボフミル・フラバル
Bohumil Hrabal(1914-1997)
『あまりにも騒がしい孤独』(Příliš hlučná samota, 1977)
せっかくたくさんの翻訳が出るようになったのだから、それらを読んでからランクインさせるべきだとは自分でも思う。きっともっと上位にいるべき人物なのだ。なにせ、クンデラとシュクヴォレツキーに並んで、「現代チェコ三大作家」に数えられているほどなのだから。この『あまりにも騒がしい孤独』はユートピアがらみの興味から手にとったのだが、ぜんぜん関係ないことばかり覚えていて、しかもそれは良書の証拠なのである。テーマは禁書ということで、ブラッドベリの『華氏451度』やハックスリーの『すばらしい新世界』に近いが、もちろんそんなことは無視していい。もっと読んでみたいと常々思っている作家のひとり。
「世界の焚書官たちが本を焼いたところで、無駄なことだ。そして、もしそれらの本が何か意味のあることを書き留めていたなら、焼かれる本たちの静かな笑い声が聞こえて来るだけだ。なぜなら、ちゃんとした本はいつも、本の外の世界を指し示しているからだ」(『あまりにも騒がしい孤独』9ページ)
085.マーク・トウェイン
Mark Twain(1835-1910)
『トム・ソーヤーの冒険』(The Adventures of Tom Sawyer, 1876)、『ハックルベリ・フィンの冒険』(Adventures of Huckleberry Finn, 1885)

ハックルベリ・フィンの冒険―トウェイン完訳コレクション (角川文庫)
- 作者: マークトウェイン,大久保博
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2004/08/01
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (18件) を見る
『トム・ソーヤーの冒険』ばかりが有名だが、あれはべつに大人が読んでもおもしろいような代物ではないと思っている(ちなみにゴールディングの『蠅の王』も、似たような理由で嫌いだ。あれは翻訳もひどい)。はっきり傑作だと言えるのは『ハックルベリ・フィンの冒険』のほうで、これを読まなかったらマーク・トウェインという作家のイメージは悪いままだったろう。ハックは以後連綿とつながる「アメリカの不良」たちの先頭に立つべき人物で、彼がいなかったらサリンジャーもブコウスキーもいなかったのでは、と、誇張でなしに思っている。
「よし、それなら、オレは地獄に行こう」(『ハックルベリ・フィンの冒険』467ページ)
084.アンリ・ド・レニエ
Henri de Régnier(1864-1936)
『水都幻談』(Esquisses vénitiennes, 1906)
レニエがすばらしいのか、翻訳した青柳瑞穂がすばらしいのか、『水都幻談』ほど美しい本はなかなかない。森鷗外のような雅文体で語られるヴェネツィアの風景は、まさに「幻談」、この世のものとは思えないほどだ。今回のランキングからは除外したが、青柳瑞穂にはアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』の翻訳もあり、こちらもすばらしい訳業である。聞くところによると堀口大學の弟子だという。納得。
「おお、ヴェネチアよ、この鍵こそ、われが汝の美しさをよそに眺むるただ一介の通行人にはあらで、汝が麗はしの魔術の永遠の囚れ人たるの証なればにや、われ、汝が妖美の標章たるこの鍵を、肌身はなさぬ護符とも、わがうれしき囚れの身の印形とも思ひて、かくは得々持ち歩くなり」(「鍵」より、『水都幻談』43ページ)
083.ダグラス・アダムス
Douglas Adams(1952‐2001)
『銀河ヒッチハイク・ガイド』(The HitchHiker's Guide to the Galaxy, 1979)

- 作者: ダグラス・アダムス,安原和見
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2005/09/03
- メディア: 文庫
- 購入: 39人 クリック: 347回
- この商品を含むブログ (371件) を見る
まだ『銀河ヒッチハイク・ガイド』しか読んでいないが、ウッドハウスへの敬愛を隠そうともしないこの作家にはかなりの好感を抱いている。文章中のユーモアはやはりウッドハウスほどではないが、それでも読んでいてげらげら笑うこともあり、大変愉快な作家。SFというのはどうもユーモア文学と親和性が高いような気がしていて、「ほらふきおじさん」ことR・A・ラファティの『宇宙舟歌』なんかも思い出される。早逝が惜しまれる作家で、『銀河ヒッチハイク・ガイド』以外のシリーズはほとんど手に入れるのが難しい。
「「あの」アーサーは口を開いた。「えーと……」みょうな気分だった。人妻と励んでいるまっさいちゅうに、いきなり相手の旦那が部屋にふらりと入ってきて、ズボンをはき替え、ふたこと三ことなにげなく天気の話などして、そのまままた出ていったときのような」(『銀河ヒッチハイク・ガイド』206ページ)
082.ジョン・アーヴィング
John Irving(1942-)
『ガープの世界』(The World According to Garp, 1978)、『ピギー・スニードを救う話』(Trying to Save Piggy Sneed, 1996)

- 作者: ジョンアーヴィング,John Irving,小川高義
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2007/08
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
アーヴィングをこんなところに置いておいたら、ぜったいだれかに怒られるぞ、と自分のなかで声が響いている。でも、そんなに冊数を読んでいないのだから仕方がないのだ。村上春樹の愛着や翻訳で有名だが、この作家の創りあげる巨大な構築物は、むしろディケンズのそれに近いと感じている。「作家の介入」という観点からは、ミラン・クンデラが好きなひとにぜひ読んでもらいたい。短篇集『ピギー・スニードを救う話』の表題作はすばらしいもので、この作品集はやはりクンデラの『可笑しい愛』を思わせる。現代最高の作家のひとりであることは疑いない。
081.ディーノ・ブッツァーティ
Dino Buzzati(1906-1972)
『シチリアを征服したクマ王国の物語』(La famosa invasione degli orsi in Sicilia, 1945)

- 作者: ディーノ・ブッツァーティ,天沢退二郎,増山暁子
- 出版社/メーカー: 福音館書店
- 発売日: 2008/05/20
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 20回
- この商品を含むブログ (23件) を見る
ブッツァーティといえば『タタール人の砂漠』だが、じつはまだ読んでいない。わたしが彼を推す理由はただひとつ、この『シチリアを征服したクマ王国の物語』である。福音館文庫に入っている、というだけで笑いがこみあげてくるような奇妙な本で、作家自身によって描かれた挿絵(やけにうまい)が、物語に文字通り彩りを添えている。なかでもぜったいに見てもらいたいのが、化け猫に食われるくらいなら、と、「みずからすすんで谷底に身投げするクマ」の絵。
080.ミハイル・ブルガーコフ
Mikhail Bulgakov (Boulgakov)(1891-1940)
『悪魔物語・運命の卵』(Дьяволиада, 1924. Роковые яйца, 1925)、『犬の心臓』(Собачье сердце, 1925)、『巨匠とマルガリータ』(Мастер и Маргарита, 1976)

- 作者: ミハイル・A・ブルガーコフ,水野忠夫
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2012/01/24
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (26件) を見る
わたしが最近熱心に読んでいたことを知るひとは、もっと上位を予想していたかもしれない。だが、わたしがブルガーコフを読むのは、ホフマンのと同じ気やすさからなのだ。つまり、なにも考えずに一気に読むことができる、極上の娯楽としての文学である。とはいえ、ホフマンよりはずっと輝く一文が多い。とくに『巨匠とマルガリータ』にはチェスタトンの『木曜日だった男』を彷彿させるようなところがあり、いつの時代にも不足していて、しかもいくらあっても困らない、こういった類稀な怪奇小説を読めることは心底喜ばしい。
「犬はその黒猫に我慢できなくなって大きな声をあげて吠えたので、男は驚いて跳びあがった。
「あい!」
「こら、ひっぱたくぞ! どうぞ、ご心配なく、この犬は咬みつきませんから」
《おれが咬みつかないだと?》犬は驚いた」(『犬の心臓』33ページ)
079.レフ・トルストイ
Leo Tolstoy (Léon Tolstoï )(1828-1910)
『イワンのばか』(Сказка об Иване-дураке и его двух братьях, 1885)、『クロイツェル・ソナタ/悪魔』(Крейцерова соната, 1889. Дьявол, 1889)
トルストイがこんなに低いわけがないでしょう、と言われる気がするが、大した冊数を読んでいないのだから仕方がない。『人生論』は高校生のときに中断したまま、結局一度も読み終えたことがないのだが、それでもわたしの考え方に大きな影響を与えた一冊である。「クロイツェル・ソナタ」は愛を公言したくなるような傑作で、同じ文庫に収められた「悪魔」は説教くささ全開の、読んでいて目に涙がたまるような作品である。先日読んだヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』のおかげで『戦争と平和』に大変興味を持ったので、2015年中には手にとってみたいと考えている。
「音楽は自分自身を、自分の真の状態を忘れさせ、自分のではない何か別の状態へ運び去ってくれるのです。音楽の影響で、実際には感じていないことを感じ、理解できないことを理解し、できないこともできるような気がするんですよ」(「クロイツェル・ソナタ」より、『クロイツェル・ソナタ/悪魔』133~134ページ)
078.ジェイムス・クリュス
James Krüss(1926-1997)
『笑いを売った少年』(Timm Thaler, 1962)
ケストナー、エンデとともに「ドイツ三大児童文学作家」に数えられていることは、「3冊で広げる世界:大人が読む児童文学」で書いたとおりだ。『涙を売られた少女』に結局まだ手を出していないので、自戒の念をこめてぜったいに読むべきだとここに記しておく。ケストナーやエンデのような作家が与えてくれる満足を得られる、というだけでも、稀有な存在であるのはまちがいないではないか。刊行元の未知谷はわたしも大ファンのすばらしい出版社で、編集者で社長の方に一度だけお会いしたことがあるのだが、わたしなんかよりもよほどたくさんの本を読んでいる、と確信をこめて言える稀代の知識人である。この出版社が出すものは信頼していい。
077.ケネス・グレーアム
Kenneth Grahame(1859-1932)
『たのしい川べ』(The Wind in the Willows, 1908)

- 作者: ケネス・グレーアム,E.H.シェパード,Kenneth Grahame,石井桃子
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2002/07/18
- メディア: 単行本
- 購入: 6人 クリック: 32回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
石井桃子というのは不思議なひとで、彼女が訳した本は、ときどき原書よりも息長く日本で読み継がれている。顕著な例がエレノア・ファージョンで、宮﨑駿も『本へのとびら』のなかで指摘していた。このケネス・グレーアムは英語圏でもいまでも愛されつづけているが、英語で読んでもこれほど気に入ったかどうかは怪しいものだ。なにせ、モグラがウサギに向かって、こんな悪口を言う箇所があるのだ。「ネギと煮ちゃうぞ。ネギと煮ちゃうぞ」。原文では「Onion Sauce!」なのだが、「ネギと煮ちゃうぞ」の鮮烈さには到底かなわないだろう。
「「とまれ!」かなりの年とみえるウサギが、生垣のすきまから声をかけました。「私用道路の通行賃六ペンス!」が、たちまち、そのウサギは、ウサギなんかしりめにかけて先をいそぐモグラに、ひっくりかえされてしまいました。なにごとがおこったんだろうと、いそいで穴から顔をのぞかせた、ほかのウサギたちもいましたが、モグラは、それさえばかにしながら、生垣についてどんどんいきます。「ネギと煮ちゃうぞ。ネギと煮ちゃうぞ。」モグラは、からかうように、こんなことをいうと、ウサギたちが胸のすくような返答を思いつかないうちに、もういってしまいました」(『たのしい川べ』14ページ)
076.H・G・ウェルズ
Herbert George Wells(1866-1946)
『タイム・マシン』(編纂)、『盗まれた細菌/初めての飛行機』(編纂)

- 作者: ハーバート・ジョージウェルズ,Herbert George Wells,南條竹則
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2010/07/08
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 5回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
SF界の巨匠というイメージの強いウェルズではあるが、わたしにとっての彼は、ちょうどポーのような短篇の名手である。まだSF作品をほとんど読んでいないというのが理由であり、わたしの偏見まみれのリストにはちょうどいい位置だと感じている。チェスタトンやバーナード・ショー、マックス・ビアボウムといった作家たちと親しい友人だったということもあり、交流関係も含め、今後もっと親しんでいきたいと思っている。
「「真の芸術家は」と絵は言った。「つねに無知な人間だ。自分の仕事について理屈をこねまわす芸術家は、もはや芸術家じゃなくて批評家だ。ワーグナーは……おい――その赤い絵の具をどうする気だ?」」(「ハリンゲイの誘惑」より、『盗まれた細菌/初めての飛行機』51~52ページ)
075.レーモン・ラディゲ
Raymond Radiguet(1903-1923)
『肉体の悪魔』(Le Diable au corps, 1923)、『ドルジェル伯の舞踏会』(Le Bal du comte d'Orgel, 1924)
かつて友人がラディゲを評して、「二十歳を超えて読むと絶望する」と言っていた。新潮文庫版の『白痴』だったと思うが、坂口安吾も同様のことを言っている。たしかに、こんなものを二十歳で書いてしまうというのはとんでもないことで、友人(愛人?)であったジャン・コクトーの嘆きも頷ける。ラディゲの恐ろしさは、執筆年が同じである処女作と遺作のあいだの圧倒的乖離にある。一人称で主観ばりばりに実体験を綴っていた『肉体の悪魔』が、同じテーマを扱った『ドルジェル伯の舞踏会』では、客観的な三人称小説に変わっているのである。かつて語られていた迸る情熱を達観する姿は、背筋が寒くなるほどである。
「ボートに横になると、生まれて初めて死にたくなった。だが、生きることができないのと同じく死ぬこともできず、慈悲深い殺人者が来てくれればいいと思っていた」(『肉体の悪魔』144ページ)
074.イアン・マキューアン
Ian McEwan(1948-)
『アムステルダム』(Amsterdam, 1998)、『初夜』(On Chesil Beach, 2007)
マキューアンはわたしの親しい友人の敬愛する作家で、読んでいるといつも彼のことを考えてしまい、どうも自分のお気に入りの作家という印象がない。おもしろいことはわかっているのに、いまだに『恥辱』しか読んだことのないクッツェーにも同じことが言える(しかも同じ友人の薦めで手に取った)。マキューアンについては、『贖罪』といった代表作に数えられる作品をほとんど読んでいないのだが、まどろっこしいほど長い比喩、どこまでも飾り立てられた表現の数々は、この作家の特徴を伝えるのに十分すぎるものだった。翻訳さえ可能な特徴というのは圧倒的である。だれが何語に翻訳しても、マキューアンはどこまでもマキューアンでありつづけるだろう。いつだって一言余計なのだが、その「余計さ」がたまらなく楽しく、美しいのだ。
「彼らは若く、教育もあったが、ふたりともこれについては、つまり新婚初夜についてはなんの心得もなく、彼らが生きたこの時代には、セックスの悩みについて話し合うことなど不可能だった。いつの時代でも、それは簡単なことではないけれど」(『初夜』5ページ)
073.アラン・シリトー
Alan Sillitoe(1928-2010)
『土曜の夜と日曜の朝』(Saturday Night and Sunday Morning, 1958)、『長距離走者の孤独』(The Loneliness of the Long-Distance Runner, 1959)

- 作者: アランシリトー,Alan Sillitoe,丸谷才一,河野一郎
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1973/09/03
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 33回
- この商品を含むブログ (57件) を見る
シリトーはこのリストのなかでももっとも早い時期に出会った作家のひとりで、言うなれば十代の青春の日々をともに過ごした作家である。短篇集『長距離走者の孤独』に収められた「漁船の絵」を読んだときには、もうほかの恋愛小説なんて一冊もいらないと感じたほどで、いまでも半分くらいはそう思っている。イギリスの作家ではあるが、行儀の悪さはサリンジャーやブコウスキーのような「アメリカの不良」たちとも通じていて、一昔前のようにもっとたくさんの本が気軽に手に取れるようになってくれればいいのに。『土曜の夜と日曜の朝』も、どろどろした恋愛の真っ最中に読んでいたので、思い出深い。
072.マルセル・エイメ
Marcel Aymé(1902-1967)
『マルタン君物語』(Derrière chez Martin, 1938)、『第二の顔』(La Belle Image, 1941)、『マルセル・エメ傑作短篇集』(編纂)
江戸川乱歩の絶賛によって知られるマルセル・エイメ(あるいはエメ、エーメ)は、奇想の作家として不動の地位を占めている。短篇の印象が強い作家ではあるが、生田耕作の訳した長篇作品『第二の顔』が、個人的にはいちばんおもしろかった。そこそこ幸せな生涯を送っていた中年男が、ある日望んでもいないのに美青年に変身し、だれからも認められなくなった彼が幸福な生活を取り戻すべく、かつての自分の妻を誘惑する、というとんでもない話である。短篇作品も、サーカスで働いていた小人がある日急に成長をはじめて失業する、など、変な話だらけ。
「人間の連帯などいかに嘘っぱちかを暴力的なまでの明白さにおいてとらえるためには、二十歳の頃に一度浮浪者になってみることが必要だ」(「クールな男」より、『マルセル・エメ傑作短篇集』72ページ)
071.オクターヴ・ユザンヌ
Octave Uzanne(1851-1931)
『愛書家鑑』(Contes pour les bibliophiles, 1894)
何冊も読んだことがあるのにランクインしなかった作家や、一冊しか読んでいないのにランクインしている作家は何人もいるが、短篇一作だけでこのリストに名を連ねたのはオクターヴ・ユザンヌただ一人きりである。『愛書家鑑』、初出のタイトルでは「シジスモンの遺産」には、それほどの価値がある。もともとこの作品を収録していた白水社の『書痴談義』は残念ながらほとんど稀覯本となってしまっており、奢霸都館の版はいつもどおり入手が大変なのだが、いまはポプラ社百年文庫に収録されたおかげで、ずっと手にとりやすくなった。本が好きな方、とりわけ、自分はちょっと本を愛しすぎている、なんて感じている方には、是非とも読んでもらいたい奇書。
「遺言状には但し書きがありまして、そのなかで、毎年あの方の誕生日に何人かの愛書家仲間に――という言葉を使っておられますが――故人の書斎で半日過ごし、蔵書を取り出し、頁をめくる権利を授けるという項目が書き込まれているのです。ただし入退室の際に身体検査を受けることを条件に」(『愛書家鑑』8~9ページ)
070.ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルク
Georg Christoph Lichtenberg(1742-1799)
『リヒテンベルク先生の控え帖』(編纂)

- 作者: ゲオルク・クリストフリヒテンベルク,Georg Christoph Lichtenberg,池内紀
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 1996/07
- メディア: 新書
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
リヒテンベルクのことは、ショーペンハウアーの『読書について』での言及なしには絶対に知ることもなかっただろう。「名言集」や「格言集」といった類の本は反吐が出るほどに嫌っているのだが、この「控え帖」は予期せずして出版されてしまった個人的なノートであり、その点ではヴァレリーの『カイエ』とも通じている。だれかがどこかから抜き出したというわけでもなく、他人の目に触れることを前提にしていないということは、余計な説明や装飾を文章から省くことにもなり、思考のもっとも濃密な箇所だけを抽出した、言わばエスプレッソのようなものを生み出す。それが何ショットも集められて形づくられたのがこの本なわけだが、編纂者が抜群の翻訳家でありアンソロジストでもある池内紀なので、胃もたれする心配もない。ネタ帳かのように冗談ばかりが溢れた本書は、同じ池内紀の編纂になる『尾崎放哉句集』とも、どこかで繋がっている気がしてならない。
「そのスープときたら、ひどい味のしろものだった。将軍か国王だったら、とっさに毒殺を恐れただろう」(『リヒテンベルク先生の控え帖』185ページ)
069.アンドレ・ブルトン
André Breton(1896-1966)
『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』(Manifeste du surréalisme, 1924)、『ナジャ』(Nadja, 1928, 1963)、『思考の表裏』(初出:La Révolution Surréaliste N°12, 1929)、『性についての探究』(Recherches sur la sexualité (1928-1932), 1990)
アンドレ・ブルトンが結局なにをしたひとなのか、いまだにはっきりとした考えが浮かばないのだが、ひとつだけ言えるのは、彼はアルフレッド・ジャリ(『超男性』)やレーモン・ルーセル(『ロクス・ソルス』)といった作家たちを世に紹介するという、大きな役割を果たしたということだ。シュルレアリスム運動についてもはっきりとしたことは言えないが、巌谷國士の『シュルレアリスムとは何か』というすばらしい名著があるので、興味のある方はそちらを読んでみてほしい。塚原史の『ダダ・シュルレアリスムの時代』もおもしろく読んだ。風景描写を排し、代替案として自分で撮影した写真を小説中に挿入する、というのは、『ナジャ』で実践された彼の文学的試みのひとつである。それ自体は失敗に終わっているように思えるのだが、常に前衛的であろうとしたその姿勢に、子どもに対する愛着のような好感を抱かずにはいられない。1920年代に友人たちを集めて芸術運動を組織し、やがてはその友人たちのほとんどに去られ、それでもなお1963年になって、かつての著作『ナジャ』に手を加えて刊行しなおした作家、それがブルトンである。
「いちどでもその内部に立ちいったことのある人なら、精神病院こそは狂人をつくるところだということを知らないはずはない。それは感化院がならず者をつくっているのとそっくりだ」(『ナジャ』163ページ)
068.J・D・サリンジャー
Jerome David Salinger(1919-2010)
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(The Catcher in the Rye, 1951)
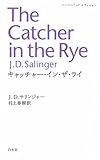
キャッチャー・イン・ザ・ライ (ペーパーバック・エディション)
- 作者: J.D.サリンジャー,J.D. Salinger,村上春樹
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2006/04
- メディア: 新書
- 購入: 11人 クリック: 73回
- この商品を含むブログ (177件) を見る
つい先日チュボスキーの『The Perks of Being a Wallflower』を読んでいて思ったのだが、サリンジャーはその影響力において、たぶんわたしが思っている以上に偉大である。まあ、偉大かどうかなんて、わたしの好みのうえではなんの関係もないのだが。ただ、ちょうど現代の日本で作家を志す若者(べつに若くなくてもいい)が、好意的にせよ否定的にせよ、すべからく村上春樹の影響から逃れられないのと同様に、一昔前のアメリカでは、サリンジャーを意識しないというのは至難のわざだったのではないか。チュボスキーはそういう世代の稀有な成功者だと思うし、村上春樹自身も、完全に彼の影響下にある(少なくとも、あった)。小島なおの短歌「春風のなかの鳩らが呟けりサリンジャーは死んでしまった」は、そんな偉大さを詠んでいるように思えるのだ(『サリンジャーは死んでしまった』より)。『フラニーとゾーイー』は高校生のとき、江國香織の小説でその名を知ったのだと記憶しているが、よくわからないままに読んで、その後読み返すことをしていない。ちょうど村上春樹の訳が出たので、近いうちに手に取りたいと思っている。
「スペンサー先生は再びうなずきを開始した。先生はまた、鼻をほじくり始めた。鼻をつまむみたいなふりをしていたんだけど、実は親指をもろに中に突っ込んでいた。部屋には僕しかいないから、そんなことをしてもべつにかまわないだろうと、先生はたぶん考えたんだと思う。いや、僕はべつにかまわないんだよ。でもさ、目の前で鼻をほじくられたりすると、とりあえずはめげちゃうよね」(『キャッチャー・イン・ザ・ライ』19ページ)
067.アンドレ・ジッド
André Gide(1869-1951)
『田園交響楽』(La Symphonie pastorale, 1919)
まだ『田園交響楽』しか記事にはしていないものの、その後の沈黙期間に『ショパンについての覚え書き』を読み、この作家の音楽への造詣の深さにぞっこん惚れこんでしまった。長生きだったからか、そんな印象はぜんぜんないが、じつは彼はヴァレリーよりも年上である。軒並み絶版ではあるものの、石川淳や堀口大學の翻訳もあるので、これからどんどん読みたいと思っている作家のひとり。
「ああ、疑心暗鬼などには耳もかさずに、現実の悪だけで満足ができたなら、人生はどんなに美しく、われわれの不幸はどんなにか忍びやすいことだろうか」(『田園交響楽』47ページ)
066.ジョゼ・サラマーゴ
José Saramago(1922-2010)
『白の闇』(Ensaio sobre a Cegueira, 1995)、『見知らぬ島への扉』(O Conto da Ilha Desconhecida, 1997)

- 作者: ジョゼ・サラマーゴ,雨沢泰
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 2008/05/30
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 7人 クリック: 41回
- この商品を含むブログ (38件) を見る
『白の闇』の映画を初めて観たとき、失礼な話ではあるが、あらためて文学の持つ力を確信した。失明する病の集団感染という、ショッキングなストーリーばかりが喧伝されがちな作品ではあるが、その真骨頂は物語に合わせてかたちづくられた文体にある。視覚なき世界では会話文が地の文に溶け込み、登場人物たちは名前を失うのである。映画もけっして駄作ではないのだが、絶対に映像化できない魅力が、この小説にはあまりに多すぎた。つまり、負け戦というやつだ。盲目と文学の関連性という括りで、ギルバート・アデアの『閉じた本』などとともに「3冊で広げる世界:盲人たちが見たもの」という記事にまとめたことがあるので、そちらも参照されたい。
「ひとつだけ意見を言わせてもらえば、わたしたちは死んでるんだわ。死んでるから目が見えないの。別の言い方がよければ、こう言ってあげようか。目が見えないから死んでるの、それは同じことなのよ」(『白の闇』272ページ)
065.アルベルト・マングェル
Alberto Manguel(1948-)
『図書館』(The Library at Night, 2006)
アルベルト・マングェルはまだそんなに翻訳されていないが、もっと読まれるべき作家だと思う。『図書館』を読んだ経験は、読んでいるときには気づきもしなかったが、その後わたしの読書の姿勢を大きく揺るがした。『不思議の国のアリス』に関する評論など、英語ではかなりの冊数が出ているので、ぜひとも読んでみたい。以下に引用した一節は、わたしの人生を変えた。一冊の本をほんとうの意味で読み終えることなど、けっしてないのだ。
「書物は、どういう順番で読むかによっても変化する。キプリングの『少年キム』のあとに読む『ドン・キホーテ』と『ハックルベリー・フィン』のあとに読む『ドン・キホーテ』は別の本である。どちらも、読む者がどんな旅を経験し、どんな友情を抱き、どんな冒険を味わったことがあるかによって、色合いが異なってくる。本は万華鏡のようにたえず変化しつづける。読みなおすたびに新たな世界が見つかり、別の形があらわれる」(『図書館』178ページ)
064.ヨシフ・ブロツキー
Joseph Brodsky(1940-1996)
『ヴェネツィア』(Watermark, 1992)

- 作者: ヨシフブロツキー,Joseph Brodsky,金関寿夫
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1996/01
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 13回
- この商品を含むブログ (28件) を見る
ヴェネツィアを舞台にした文学は驚くほど数が多いが、そのなかでも燦然と輝くのがブロツキーのそれである。このひとの詩情は、もはや舞台がヴェネツィアである必要性を感じさせない。その文章の圧倒的な密度は、読者に理解されようという色気をまったく感じさせず、ノーベル文学賞まで受賞している作家だというのに、文学的野心などまるで抱いていなかったのではないか、とまで思わせるのだ。徹底的に自分を曲げないひとだったのだと思う。わたしはこの作家とフェルナンド・ペソア、それにエステルハージ・ペーテルを並べて、「野心をまったく持たない書き手」と呼ぶのが好きだ。
「われわれの世界では、もし天使の翼がほしければ、空軍に入るくらいしか手はない」(『ヴェネツィア』87ページ)
063.ジョージ・オーウェル
George Orwell(1903-1950)
『動物農場』(Animal Farm, 1945)、『一九八四年』(Nineteen Eighty-Four, 1949)
![一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫) 一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZAgdWin2L._SL160_.jpg)
- 作者: ジョージ・オーウェル,高橋和久
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2009/07/18
- メディア: 文庫
- 購入: 38人 クリック: 329回
- この商品を含むブログ (323件) を見る
以前、このひとはたぶん冗談の通じないひとだったのだろう、と勝手に予想していた。『動物農場』って、もっと笑える本でもよかったと思うのだ。だって「豚による独裁」だなんて、ちょっとファンシーではないか。それが、あんなにも醜悪な物語になってしまうだなんて。と、勝手な予想を裏切られたことに対して勝手に憤慨していたのだが、『一九八四年』を読んでみて、このひとはまじめなときほど輝く、ということに気がついた。架空の言語イングソックの仕組みを語っているときの彼はとくに忘れがたく、軽薄さの欠片もない、理論的で重厚な物語がよく似合うのだ。それにいまのわたしたちは、ウッドハウスが対独協力という理由で第二次大戦後にイギリス国内で非難を受けていたとき、救いの手を差し伸べたのがほかならぬこのオーウェルだったことを知っている。そんな彼がユーモアを解さなかったはずがない、といまは思う。
「彼はそれまで何度も考えたように、はたして自分は狂人ではないのかと考えた。ひょっとすると狂人はたった一人の少数派そのものかもしれない。かつて地球が太陽のまわりを回っていると信ずることは狂人のしるしだった。現在では、過去は変更不可能だと信じることがそのしるし。そのように信じるのは自分ただ一人かもしれない。そして一人なら、それは狂人ということだ。だが、狂人であると考えてもそれほど動揺しなかった。恐ろしいのは同時に自分が間違ってもいるのではないかということだった」(『一九八四年』123ページ)
062.ブルース・チャトウィン
Bruce Chatwin(1940-1989)
『ウッツ男爵』(Utz, 1988)、『どうして僕はこんなところに』(What Am I Doing Here? 1989)

- 作者: ブルース・チャトウィン,池央耿
- 出版社/メーカー: 角川書店(角川グループパブリッシング)
- 発売日: 2012/06/22
- メディア: 文庫
- 購入: 13人 クリック: 479回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
そもそもどうして『ウッツ男爵』に手を伸ばしたのか、ごく最近のことなのにどうも思い出せないのだが、チャトウィンとの、とりわけ『どうして僕はこんなところに』との出会いは、その後ロシア・アヴァンギャルドへの関心へとわたしを駆り立て、ヴィーリ・ミリマノフの『ロシア・アヴァンギャルドと20世紀の美的革命』との出会いなど、すでにたくさんのものをもたらしてくれている。代表作とされる『ソングライン』はまだ読んでいないのだが、手に入る本はすでにあらかた自室に揃っているので、早めに手に取りたい。彼に教わったエルンスト・ユンガーも、その隣で控えている。
「アマゾネスと話していた伍長が戻ってきて、私たちにも下着一枚になれと命じた。まさしく、ルールなどどこにもありはしない。私は躊躇した。下着をつけていたか、確信がなかった。だが、腰に銃口をつきつけられては、下着をつけていようがいまいがズボンを脱がねばならぬと観念した。脱いでみると、私はブルックスブラザーズのピンクと白のボクサー・ショーツをはいていた」(「クーデター――物語」より、『どうして僕はこんなところに』38~39ページ)
061.ヴラジーミル・マヤコフスキー
Vladimir Mayakovsky(Maïakovski)(1893-1930)
『悲劇ヴラジーミル・マヤコフスキー』(Владимир Маяковский, 1914)、『ズボンをはいた雲』(Облако в штанах, 1915)、『背骨のフルート』(Флейта-позвоночник, 1916)、評伝:小笠原豊樹『マヤコフスキー事件』(2013)
マヤコフスキーを読むことは、わたしにとって小笠原豊樹を読むことだ。じっさいの彼自身の作品より先に『マヤコフスキー事件』を読むなど、普段のわたしだったらしないような「偏見の事前導入」をしたのだが、そのせいもあってか、この詩人に対してはぜんぜん批判的な感情を抱けない。小笠原豊樹以外が訳した作品を読めば変わるのかもしれないが、彼の翻訳があまりにすばらしいので、そんな気はぜんぜん起きない。困ったものだ。
「ぼくが欲しいのは毒だけだ、/詩を飲むに飲むこと。」(『背骨のフルート』42ページ)
060.ボリス・ヴィアン
Boris Vian(1920-1959)
『日々の泡』(L'Écume des jours, 1947)、コミック:岡崎京子『うたかたの日々』(1994)
ヴィアンを好きなわりに結局ぜんぜん読めていないのは、邦訳に不当な不信を抱いているくせして、原文ですいすい読めるほど単純な作家ではないということに尽きる。伊藤守男訳のハヤカワepi文庫版『うたかたの日々』をどうも好きになれなかったのが最大の理由で、曽根元吉訳の『日々の泡』は、訳題の詩情こそ伊東守男訳には劣るが(それでもこちらのほうが正確だ)、よっぽど読みやすいのである。チャンドラーを初めてフランス語に訳した人物であり、その反戦の歌(シャンソン)は本を読まないひとでも知っているほど、フランスでは名の知られた作家だ。最近プレイヤード叢書入りし、文学においても名実ともに「古典」の仲間入りをしたと言えるだろう。
「人はそう変わるもんじゃない。変わるのは物事だよ」(『日々の泡』250ページ)
059.スチュアート・ダイベック
Stuart Dybek(1942-)
『シカゴ育ち』(The Coast of Chicago, 2004)
現代でもっとも名を知られた翻訳家は柴田元幸だと思うのだが、その多作ぶりのわりに、わたしはあまり読んだことがない。彼の訳書が現代アメリカ文学に集中しているのが原因で、わたしは「文学はどうなっているのか」にはとてつもない興味を抱いているのだが、「“現代の”文学はどうなっているのか」ということには、はっきり言ってたいした関心がないのだ。彼の訳書では上述のブコウスキーの『パルプ』やレベッカ・ブラウンの『体の贈り物』、ミルハウザーの『イン・ザ・ペニー・アーケード』、さらには高橋源一郎との対談『柴田さんと高橋さんの小説の読み方、書き方、訳し方』も読んだが、その姿勢が変わることはない。ところが、ダイベックはそんな現代作家たちに対する偏見を後悔させるほどの詩人なのである。この作家が百年後にも同じ輝きを放っていることは疑いなく、その溢れる詩情と、それを違和感なく物語に介入させる手腕は圧倒的で、「荒廃地域」の思い出はいつまでも古びない。ダイベックを読んで、わたしは柴田元幸の慧眼に感謝したのである。
058.ニコライ・ゴーゴリ
Nikolai Gogol (Nicolas Gogol)(1809-1852)
『隊長ブーリバ』(Тара́с Бу́льба, 1835)、『鼻/外套/査察官』(Нос, 1835-36, Коляска, 1836, Шинель, 1842)
ゴーゴリはドストエフスキーの敬意によって有名なため、じっさいに手に取ったことのないひとには大変難しいことでも書いていると思われがちだが、そんなことはぜんぜんない、ぜひともソファで寝そべって読みたい作家である。光文社古典新訳文庫の『鼻/外套/査察官』は落語調に翻訳されていて、最初はわたしもちょっと拒否反応を起こしていたのだが、読んでみたらこれ以外にどう訳せばいいのか思いつかないほどの名訳であった。ドストエフスキーのユーモア作品集『鰐』はゴーゴリを強く意識した短篇集なので、好きなひとにはぜひ手に取ってみてもらいたい。『隊長ブーリバ』は翻訳も古いので、よほどコサックに興味があるのでもないかぎり読まなくてもいいと思う。
「てめえたちなんざ縄でひっくくって、粉みてえにすりつぶし、悪魔の着物の裏地や帽子のなかに詰め込んでやる!」(「査察官」より、『鼻/外套/査察官』331ページ)
057.ジャンニ・ロダーリ
Gianni Rodari(1920-1980)
『猫とともに去りぬ』(Novelle fatte a macchina, 1973)、『二度生きたランベルト』(C'era due volte il barone Lamberto ovvero I misteri dell'isola di San Giulio, 1978)
『チポリーノの冒険』が新訳復刊され、『パパの電話を待ちながら』が文庫化されるなど、どういうわけだろう、ロダーリはいまや日本の書店で、手に入りにくい作家ではぜんぜんなくなった。すべてのきっかけは2006年、『猫とともに去りぬ』が光文社古典新訳文庫にラインナップされるようになってからだと思う。もちろんちくま文庫の『ファンタジーの文法』など、その前にも翻訳はあったが、「知るひとぞ知るマイナーな作家」という印象は完全に払拭されたと言っていいだろう。平凡社からかつて刊行されていた『二度生きたランベルト』は、訳文もほんとうにすばらしい大傑作なので、いつか復刊されることを願ってやまない。
「運転手は、大急ぎで彼らをミアジーノ町まで運ぶ。そこが彼らの宿泊場所だ。18世紀のフレスコ画と19世紀絵画と20世紀の家電製品が調った、17世紀のお屋敷である」(『二度生きたランベルト』98ページ)
056.R・L・スティーヴンスン
Robert Louis Stevenson(1850-1894)
『旅は驢馬をつれて』(Travels with a Donkey in the Cévennes, 1879)、『新アラビア夜話』(New Arabian Nights, 1882)、『宝島』(Treasure Island, 1883)、『A Child's Garden of Verses』(1885)、『箱ちがい』(The Wrong Box, co-written with Lloyd Osbourne, 1889)

- 作者: ロバート・ルイススティーヴンスン,Robert Louis Stevenson,南條竹則,坂本あおい
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2007/09/06
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (31件) を見る
スティーヴンスンは無神経なやつだと、『旅は驢馬をつれて』を読んだときに思った。なんというか、ひとが嫌がることを、それと気づかずにやらかしてしまうやつだったと思うのだ。そうでなければ、なぜ哀れな驢馬のモデスチンに鞭をくれてやったことをあんなにも繰り返し書く必要があったろうか。時代が時代とはいえ、『A Child's Garden of Verses』で、なぜインド人や日本人を馬鹿にしたようなことを書く必要があったろうか。書かなくてもいいことを書き、ひとの気分を悪くしているのであり、始末に負えない。しかしわたしは、そんな無神経なところも含めて、スティーヴンスンが好きである。もちろん、あの圧倒的な『新アラビア夜話』がなければ、そこまでの愛着は感じなかったにちがいないが、いつかまたあの興奮に出会えるかも、という淡い期待が、何度も繰り返しこの著者の本に手を伸ばさせるのである。
「思うにモデスチンが満足な一歩を運ぶには、私はすくなくとも二度力をこめてなぐらねばならなかった。その附近一帯、私がたゆみなくなぐる音以外、何の物音もきかれなかった」(『旅は驢馬をつれて』24ページ)
055.ジェローム・K・ジェローム
Jerome Klapka Jerome(1859-1927)
『ボートの三人男』(Three Men in a Boat, 1889)

- 作者: ジェローム・K.ジェローム,丸谷才一
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2010/03/25
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
ユーモア文学の時代がこの男によって幕をあげられたとすれば、馬鹿笑いが大好きなわたしとしては無闇に扱うことはできない。その伝統はイギリスで、ウッドハウスによって継承・発展され、さらにはダグラス・アダムスにまで引き継がれ、いまもなお新しい作家たちを生み出しつづけている。この流れを「3冊で広げる世界:頭の悪すぎる英国紳士たち」という記事に書いたことがあるので、興味のある方にはそちらも参照してもらいたい。
「ぼくが抱えている仕事のなかには何年間もぼくの所有に属していて、しかも指のあと一つついていないものもあるのだ。ぼくは自分の仕事にたいへん誇りをもっている。ときどき仕事をとりだして、ハタキをかけてみるくらいだ。仕事の保存状態がぼくよりもよい人は、あまりいないだろう」(『ボートの三人男』218ページ)
054.スタンダール
Stendhal(1783-1842)
『赤と黒』(Le Rouge et le Noir, 1830)
いまでも忘れられないのだが、以前あるきっかけを得て「フランスの悪女たち」という括りで『赤と黒』を『ボヴァリー夫人』や『マノン・レスコー』、さらには『女と人形』などと並べたとき、ある出版社の編集の方が、「『赤と黒』に悪女なんてひとりもいませんよ!」と猛反発してこられた。びびってしまったわたしは、「でも、ほら、レナール夫人とか……」とかなんとか、ごにょごにょ言ったのだが、あのときほんとうに言うべきだったのは、「あんたはマチルドに肩入れしすぎだ!」の一言だった、といまは思う。だって、レナール夫人は悪女でしょう? なんならアンケートをとりたいくらいだ。
「あの若者には何もかもそろっている。若さだけは足りないがね」(『赤と黒』下巻、464ページ)
053.フョードル・ドストエフスキー
Fyodor Dostoyevsky (FiodorDostoïevski)(1821-1881)
『鰐』(Крокодил, 1865)、『カラマーゾフの兄弟』(Братья Карамазовы, 1880)
『カラマーゾフの兄弟』の新訳が巻き起こしたブームは、その後いろいろな古典作品の復刊にもつながったと思うので、亀山郁夫にはなんだかんだみんな感謝するべきだと思う。最初の一ページを開くのがこんなに困難な本もないが、開いてみたが最後、あとはもったいないほど速く読み終えてしまえることだろう。最近はぜんぜん手に取ることをしていないので、小笠原豊樹が訳した『虐げられた人びと』などを筆頭に、もう一度その世界に飛び込みたいと思っている。
「それに何より、鼻高々の小説家を追いつめ、首を絞めるのは、物語のディテールです。現実は、つねにあふれかえるディテールです。でも、それはいつだって、まるでどうということのない下らないがらくたに見えるものなのです」(『カラマーゾフの兄弟』四巻、583~584ページ)
052.マルセル・パニョル
Marcel Pagnol(1895-1974)
『Marius』(1929)、『Fanny』(1931)、『César』(1946)、『La Gloire de mon père』(1957)
フランス語の原書ばかりで変な感じだが、この作家は『Petit Nicolas』くらいしか読めなかった当時のわたしにも楽しむことのできた数少ない作家のひとりで、いわばフランス語で本を読むことを直接的に教えてくれたひとでもある。『Marius』三部作の感動はいまだに忘れがたく、『La Gloire de mon père』ほどすばらしい幼年期の回想には、いまだに出会ったことがない。最近めっきりフランス語で小説を読むことをしなくなってしまったので、またパニョルにすがってみようと考えている。
「マリユス、評判っていうのはマッチみたいなものなんだ。一度きりしか役に立たない」(『Marius』167ページ)
051.ジャン・コクトー
Jean Cocteau(1889-1963)
『ポトマック』(Le Potomak, 1919)

- 作者: ジャンコクトー,Jean Cocteau,渋澤龍彦
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2000/02
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
コクトーはその多才さもあって語るべきことの多い人物ではあるが、わたしにとってもっとも強い印象は、『ポトマック』の詩人としての彼である。わたしは『ポトマック』を読むまで、散文も詩であるということを知らずにいたような気がする。文章に耽溺することの快楽を、もっとも直接的なかたちで教えてくれた作家のひとりだ。その詩はいまも、わたしのなかで新鮮に鳴り響いている。堀口大學の詩集・随筆集『虹消えず』に、コクトーが来日したときの回想が描かれており、トランクにヴェルヌの『八十日間世界一周』の登場人物フィリアス・フォッグの名前が書いてあったなど、愉快なエピソードが伝えられている。
「船ならばドックに入っているほうが、ボナパルトならば兵営時代のほうが、ダビデならば山羊の乳をしぼっている時のほうが、クリストフ・コロンブスならばパロス港にいる時のほうが、シンドバッドならばまだ自分の家にいる時のほうが、それぞれ僕には好ましかった」(『ポトマック』12ページ)
050.ロジェ・グルニエ
Roger Grenier(1919-)
『シネロマン』(Ciné-roman, 1972)、『夜の寓話』(La Salle de rédaction, 1977)、『フラゴナールの婚約者』(La Fiancée de Fragonard, 1982)
ロジェ・グルニエはフランスに住んでいたころに、パリのブックオフで叩き売られているのを見つけて、三冊立て続けに読んだ。短篇集『フラゴナールの婚約者』に収められた「沈黙」という作品が群を抜いておもしろく、それ以外にもシューベルトへの敬愛に満ちた作品なども多くあり、すばらしい時間を過ごせた記憶がある。『ユリシーズの涙』について記事を書いていないことにいまさらながら気づいたので、機を見てもう一度読んでから書いてみたい。宮下志朗訳ということでは『写真の秘密』にもまだ手を出しておらず、楽しみにしている。チェーホフを愛し、『シネロマン』では映画、『写真の秘密』では写真について語り、そして短篇作品ではシューベルトやマーラーについて饒舌をきわめるという、じつに広範な芸術に通じた文化人である。
「プランを変えよう。私の主人公は見失った女性を探しに出かけないことにする。彼は一生、彼女のことを想像しつづけるだけで満足する。それはチェーホフだ。すべてを捨ててモスクワへ、よりよい生活にむけて出発するのだ、と言う。が、けっして実行はしない」(「沈黙」より、『フラゴナールの婚約者』206ページ)
049.エドガー・アラン・ポー
Edgar Allan Poe(1809-1849)
『黒猫/モルグ街の殺人』(編纂)
パターン化された構成を持っている作家というのは、それが気に入るとどこまでも抜け出せなくなってしまう。ポーの怪奇小説はまさしくそれで、江戸川乱歩の私淑も頷けるというものだ。まず一般的な会話からはじめて、そこから事件へとつなげていく。「邪鬼」を読んだときの衝撃は忘れられない。乱歩は「赤い部屋」という短篇を書いているのだが、これなんかはまさしくポーの構成である。パターンという意味では、デュ・モーリアの怪奇小説にも傍目にわかりやすい構造があり、こちらの場合、最後のページを読み終えた直後に、最初のページに立ち戻るという衝動に駆られる。短篇集『鳥』一冊を読むだけでも、彼女の目指したものは伝わってくることだろう。ところでポーに関しては、「雑記:ぼくはおしゃれなブックラバー」にて紹介したOut of Printというアメリカの通販サイトで、色々なグッズが売られている。先日polkadot(水玉)をもじった「Poe-kadot」なるトートバッグを注文してしまった。デザインが秀逸。
「人間は、してはいけないという理由で、してはいけないことをする」(「邪鬼」より、『黒猫/モルグ街の殺人』64ページ)
048.ピエール・ルイス
Pierre Louÿs(1870-1925)
『女と人形』(La femme et le Pantin, 1898)、「女性のための社交術」(Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, 1926)、「書庫の幻」(短篇)
これはアンドレ・ブルトンが『性についての探究』で語っていたことでもあるが、ピエール・ルイスをただの官能小説作家と混同するのは誤解も甚だしい。『女と人形』は『マノン・レスコー』とともに文学史に燦然と輝く悪女の星であり、短篇「書庫の幻」はフロベールの「愛書狂」と並んで愛書小説の傑作である。鈴木信太郎の訳文に馴染めないというだけの理由で、代表作と目される『ビリチスの歌』を手に取れずにいたが、これまでに読んだ小品は忘れがたいものばかりだ。沓掛良彦訳の『アフロディテ』など、読みたいものはまだまだたくさんある。
「どんなことがあっても付き合ってはならない女に二種類あります。まず第一に君を愛していない女、それからもう一つは、君を愛している女です。――この両極の間に、可愛らしい女が無数にいる。ところが私たちはそういう女の値打ちがわからないんです」(『女と人形』39ページ)
047.ギヨーム・アポリネール
Guillaume Apollinaire(1880-1918)
『アポリネール詩集』(編纂)
日も暮れよ、鐘も鳴れ。月日は流れ、わたしは残る。わたしはパリに住んでいたころ、電車を乗り継いでミラボー橋を見に行ったことがある。いま思えば、パリに対する憧れは、この詩を読んだときに初めて植えつけられたような気がする。新潮文庫から出ているアポリネールの詩集を、高校生のわたしはただ安いからというだけの理由で買い、かっこつける意味も含めて、鞄に潜ませ持ち歩いていたのだ。この詩人は、ちょっと特別である。
「命ばかりが長く、希望ばかりが大きい」(「ミラボー橋」より、『アポリネール詩集』51~53ページ)
046.アルトゥール・ショーペンハウアー
Arthur Schopenhauer(1788-1860)
『読書について』(extracts from Parerga und Paralipomena, 1851)

- 作者: アルトゥールショーペンハウアー,Arthur Schopenhauer,鈴木芳子
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2013/05/14
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (13件) を見る
『読書について』は大著『余録と補遺』の抜粋でしかないので、それしか読んだことのないもぐりがなにかを語ろうというのは心底まちがっていると、自分でも思う。だが、『読書について』ほど昨今の出版業界をめぐる自分の不満を代弁してくれた本はなく、読む前の偏見が嘘のよう、いまでは全幅の信頼を寄せてしまっているのだ。わたしにとって読書は快楽であって、こんなリストを作るためにしていることではない。矛盾しているが、そのことを忘れないようにしたい。
「私たちが本を読む場合、もっとも大切なのは、読まずにすますコツだ」(『読書について』145ページ)
045.エステルハージ・ペーテル
Esterházy Péter(1950-)
『ハーン=ハーン伯爵夫人のまなざし』(Hahn-Hahn grófnő pillantása, 1992)

ハーン=ハーン伯爵夫人のまなざし―ドナウを下って (東欧の想像力 3)
- 作者: ペーテルエステルハージ,早稲田みか
- 出版社/メーカー: 松籟社
- 発売日: 2008/11/30
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
度肝を抜かれる読書体験というのは、たいていこういう、だれなのか想像もつかないような作家からもたらされる。なんの期待も抱かずにページを開いた分、その衝撃に心底打ちのめされることになったのだろう。でも、賭けてもいいが、エステルハージ・ペーテルがだれなのかを知っている博識な読者が読んだって、『ハーン=ハーン伯爵夫人のまなざし』には度肝を抜かれるはずだ。じわじわ効いてくるというのはこういうことで、読みはじめは退屈、途中からようやく楽しみ方がわかってきて、読み終えたずいぶんあとになって、じつはとんでもない本を読んでいたのでは、という気になってくる。そしていま、この作家は不動の地位を得た。先日、白水社から『女がいる』という小説が刊行され、読むのを楽しみにしている。
「もうたくさんです。ドナウ川など存在しない、あるのはブレーク川とブリガッハ川だ、というのが簡潔明快な主張でしょう。すると、ドナウ川はフィクション、詩なのです」(『ハーン=ハーン伯爵夫人のまなざし』23ページ)
044.アンリ・トロワイヤ
Henri Troyat(1911-2007)
『仮面の商人』(Le Marchand de masques, 1994)
伝記作家として名の知られた彼の伝記を、わたしはまだひとつも読んだことがない。だが、『仮面の商人』の体験は、いきなりこの作家にこんな位置を与えることになった。小笠原豊樹が訳した三冊の小説のほか、フランスで刊行されたばかりの新版も取り寄せているところで、いま一番読むのを楽しみにしている作家である。
「ここでは、芸術家と商人の混同が全面的に行われている。作家が購買者に本を直接売り込んだりしないのは当然だが、たいていの作家たちは、売り捌かれる本の部数が多いほど、その本には価値があると信じているらしい。ヴァランタンのような純粋な詩人は、ぜんぜん売れないことを誇りに思うしかない」(『仮面の商人』69ページ)
043.ジェイン・オースティン
Jane Austen(1775-1817)
『分別と多感』(Sense and Sensibility, 1811)、『高慢と偏見』(Pride and Prejudice, 1813)

- 作者: ジェインオースティン,Jane Austen,中野康司
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2003/08
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 37回
- この商品を含むブログ (42件) を見る
オースティンはブロンテ姉妹などとともに語られることが多いが、ヴァージニア・ウルフが『自分だけの部屋』で執拗に繰り返していたとおり、その質において圧倒的に異なる。いったい誰が、『嵐が丘』と『高慢と偏見』を並べようなどと最初に思いついたのだろうか? ただ同時代の女性作家だという理由だけで、いまだに彼女たちが並べられつづけているのは、女性作家に対する偏見の根深さを物語っているように思えてならない。オースティンの生き生きとした登場人物たちはページにその姿を現していないときにさえなにをしているかが想像できるほどであり、彼女の小説を読んでいて登場人物を混同するようなことはけっして起こらない。中野康司のすばらしい翻訳は、今後百年読み継がれるべきだと思う。フォースターが私淑した作家であり、その敬意は『小説の諸相』において余すところなく語られているそうなので、近いうちに手に取りたいと思っている。
042.イワン・ツルゲーネフ
Ivan Turgenev (Tourgueniev)(1818-1883)
『初恋』(Первая Любовь, 1860)、『父と子』(Отцы и дети, 1862)
『父と子』の圧倒的なロマンティシズムは、それまでわたしが抱いていた「暗くて陰鬱なロシア文学」のイメージを徹底的に瓦解させた。史上初めての「ニヒリスト」であるバザーロフは、恋愛感情を否定し、その姿勢を頑なに貫くのだが、その過程が逆説的なことに、とてもロマンティックに描かれているのだ。サイードが『知識人とは何か』のなかで、「作中で知識人を形成した作品」として、フロベールの『感情教育』とジョイスの『若い藝術家の肖像』とともに挙げていたことも忘れがたい。
「死は古い喜劇だが、一人一人には新しい姿で訪れる」(『父と子』333ページ)
041.プラトン
Plato (Platon)(427-347 B.C.)
『ソクラテスの弁明』(Ἀπολογία Σωκράτους)、『クリトン』(Κρίτων)、『プロタゴラス』(Πρωταγόρας)、『ゴルギアス』(Γοργάς)、『饗宴』(Συμπόσιον)
プラトンはまだ哲学が現在のような学問としての地位を確立する前、字義どおりに「知を愛する」行為であったころの作家なので、肩肘張ることなく読むことができ、とても好きだ。現代の哲学は学者によってさえ定義がまちまちな専門用語に溢れている(ような気がしている)が、プラトンを読んでいるかぎりそんな困難にぶつかることはない。いまのところ、わたしがとくに好きなのは『ゴルギアス』で、討論とはなんたるかを知りたいすべてのひとが読むべきだと思っている。ヴァレリーによるあまりにも彼らしいオマージュ、『エウパリノス・魂と舞踏・樹についての対話』も忘れずに薦めておきたい。
「人は、自分が不正を受けることを警戒するよりも不正をはたらくことのほうを警戒して避けなければならぬ。人間がなににもまして心がけねばならぬのは、公私いずれにおいても、すぐれた人間だと思われることではなく、じっさいにすぐれた人間であるということだ」(『ゴルギアス』475ページ)
040.ミラン・クンデラ
Milan Kundera(1929-)
『可笑しい愛』(Směšné lásky, 1963)、『存在の耐えられない軽さ』(Nesnesitelná lehkost bytí, 1984)、『ほんとうの私』(L'Identité, 1998)、『無知』(L'Ignorance, 2003)

- 作者: ミランクンデラ,Milan Kundera,千野栄一
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/11
- メディア: 文庫
- 購入: 30人 クリック: 312回
- この商品を含むブログ (162件) を見る
今月『冗談』が岩波文庫に入ったのは、ひとつの偉業だと思っている。存命の作家が岩波文庫に入るというのは、普通のことではないと思うのだ。しかもそれが、ちょうど読みたいと思っていた『冗談』だなんて! 天啓としか思えない。中毒性の高い作家で、一時期かなり熱心に読んでいたのだが、久しく遠ざかってしまっていた。セルバンテスの『ドン・キホーテ』は、この作家のしつこいほどの後押しがなければ、手にとらなかったかもしれない。何年ぶりか数える気もおきない新作小説『La Fête de l'insignifiance』も今年フランスで発表されたので、西永良成氏は大忙しだろうと期待している。
「秘密なものとはもっとも共通の、もっとも凡庸な、もっとも反復的な、そして万人に固有のものなのだ。身体とその欲求、病気、癖、たとえば便秘、あるいは月経など。ぼくらが恥ずかしそうにそんな私的なことがらを隠すのは、それが個人的なものだからではなく、逆に嘆かわしいほどなんとも非個人的なものだからだ」(『ほんとうの私』129ページ)
039.ジャン・ジロドゥ
Jean Giraudoux(1882-1944)
『オンディーヌ』(Ondine, 1939)

- 作者: ジャンジロドゥ,Jean Giraudoux,二木麻里
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2008/03/12
- メディア: 文庫
- クリック: 10回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
戯曲というのは詩と並んで、小説よりも古い文学形式なのだということを、頭で理解はしていても実感することは少ない。重要なのは、「詩と並んで」という点である。ジロドゥを読んでいるときに感じる恍惚感は、詩によって得られるそれにあまりに似ているではないか。イヨネスコもそうだが、文庫化するなりして、もっと手に取りやすくするべき作家の筆頭だ。『ガリレオの生涯』を書いたブレヒトは、そういう意味ではかなり優遇されている。『テッサ』や『トロイ戦争は起こらない』だけでも、なんとかならないものか。
「不幸だということは、だから幸福じゃないということにはならないの」(『オンディーヌ』210~211ページ)
038.ミヒャエル・エンデ
Michael Ende(1929-1995)
『モモ』(Momo, 1973)、『スナーク狩り』(Die Jagd nach dem Schlarg, 1988)、『魔法のカクテル』(Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch, 1989)

- 作者: ミヒャエル・エンデ,大島かおり
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2005/06/16
- メディア: 新書
- 購入: 41人 クリック: 434回
- この商品を含むブログ (291件) を見る
エンデはドイツの児童文学作家ということでケストナーと並列されることが多いが、エンデは超自然的な要素を物語に持ち込むので、じつはその作風はケストナーとはまったく異なる。『モモ』や『はてしない物語』がとくに有名だが、ルイス・キャロルの『スナーク狩り』の翻案など、大人のための奇妙な作品も数多く、それに惹かれてわたしは全集を揃えてしまったほどだ。いろいろな側面を持つ作家ではあるが、やはり『モモ』が圧倒的で、これを読んだことのないひととは友だちになれない、とさえ思う。
「光を見るためには目があり、音を聞くためには耳があるのとおなじに、人間には時間を感じとるために心というものがある。そして、もしその心が時間を感じとらないようなときには、その時間はないもおなじだ。ちょうど虹の七色が目の見えない人にはないもおなじで、鳥の声が耳の聞こえない人にはないもおなじなようにね」(『モモ』236ページ)
037.ヘルマン・ヘッセ
Hermann Hesse(1877-1962)
『車輪の下で』(Unterm Rad, 1906)、『デミアン』(Demian, 1919)、『シッダールタ』(Siddhartha, 1922)、『ヘッセの読書術』(編纂)
『デミアン』を読んでいるかいないかで人生が変わってくる、と思うのは、わたしだけではないはずだ。立て続けに読んだからそんな印象を抱いているのかもしれないが、『カラマーゾフの兄弟』を凝縮したような話で、太宰治の『人間失格』にもちょっと通じているような気がしている(「わざ、わざ」)。読んだまま結局記事にしていないムージルの『奇宿生テルレスの混乱』やケストナーの『飛ぶ教室』と並んで、『デミアン』はギムナジウムを舞台にした文学の最高傑作のひとつだ。また、『ヘッセの読書術』で世界文学全集を編むヘッセの姿は、好きなひとなら必見。あれほどテンションの高いヘッセにお目にかかることはない。
「大多数の人々の道は楽で、ぼくたちの道は苦しい。――しかしぼくたちは進もう」(『デミアン』169ページ)
036.ウジェーヌ・イヨネスコ
Eugène Ionesco(1909-1994)
『La Cantatrice chauvesuivi de La Leçon』(1950, 1951)、『Contes 1·2·3·4』(2009)

LA Cantatrice Chauve: Anti-Piece ; Suivi De, LA Lecon : Drame Comique (Collection Folio, 236)
- 作者: Eugene Ionesco
- 出版社/メーカー: Gallimard
- 発売日: 2002/06
- メディア: マスマーケット
- この商品を含むブログを見る
イヨネスコは刊行形態に恵まれておらず、日本ではいまだに全集以外では読むすべのない作家で、そのためぜんぜん名を知られていないが、『ゴドーを待ちながら』のベケットやアルチュール・アダモフとともに「不条理演劇」を代表する作家であり、フランスではひょっとしたらベケットよりも有名だ。その理由が、大変笑えることに、日本とは対照的に刊行形態に恵まれているからなのである。べケットがMinuits社という文学好きのための出版社(日本で言えば岩波書店?)から刊行されているのに対し、イヨネスコは業界でも最大手のGallimard社(言わば新潮社?)から、それこそ駅前の書店で売られている新潮文庫のように、手に取りやすい形態で広く普及されているのである。とはいえその作風は、こんなものを普及させて大丈夫か、と不安になるほどハチャメチャで、徹底して愉快である。不条理だとかなんだとかは、じっさいにこの愉快さに触れてみると、じつにどうでもいい問題だ。
「イギリスの肘掛け椅子のあるイギリスの資産家の家のイギリスの夕べ。イギリス人のスミス氏はその椅子に腰掛けてイギリスのスリッパを履き、イギリスの暖炉の側でイギリスのパイプをふかしながらイギリスの新聞を読んでいる。彼はイギリスのメガネをかけて、イギリスの灰色の口ひげを生やしている。彼の隣にはまた別のイギリスの肘掛け椅子があり、イギリス人のスミス夫人がイギリスの靴下を繕っている。イギリスの長い沈黙の後、イギリスの時計がイギリスの17時を告げる」(『La Cantatrice chauvesuivi de La Leçon』11ページ)
035.ジョルジュ・ペレック
Georges Perec(1936-1982)
『煙滅』(La Disparition, 1969)

- 作者: ジョルジュペレック,Georges Perec,塩塚秀一郎
- 出版社/メーカー: 水声社
- 発売日: 2010/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 43回
- この商品を含むブログ (26件) を見る
『煙滅』の顕著な例のとおり、ペレックの言語遊戯の完成度の高さは常軌を逸していて、それゆえにわたしなどは、これは大きな声で言うのがためらわれるが、純粋な小説として彼の作品を楽しむことができない。それでも「雑記:ペレックが死ぬまでにしたい50のこと」でも紹介したとおり、この作家が大変愉快な人物であることは疑いようもない。わたしはなかでも、「冬の旅」という短篇(『書肆風の薔薇第5号:ウリポの言語遊戯』所収)が好きだ。『煙滅』と対をなす『Les revenentes』という作品があるのだが、塩塚秀一郎が最近やけに静かな理由は、ひょっとしてこれなのではないか、と勘繰っている。
「「なあ、スファンクスよ」アウエはラカンを読んだことがあったので、こう声をかけた。「そう焦らず、まずはお務めを果たせよ。謎をかけるんだろ」」(『煙滅』43ページ)
034.ホメロス
Homer (Homère)(8th century B.C.)
『イリアス』(Iλιάς)、『オデュッセイア』(Ὀδύσσεια)、伝記:ヘロドトス(伝)『ホメロス伝』(2nd century)

- 作者: ホメロス,Homeros,松平千秋
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1992/09/16
- メディア: 文庫
- 購入: 11人 クリック: 53回
- この商品を含むブログ (54件) を見る
レーモン・クノーが『あなたまかせのお話』に収められたインタビューで唱えていた文学論に、「すべての文学作品はイリアス型とオデュッセイア型に大別できる」、というものがある。大雑把に言うと、一人の人物に焦点を当てたのはオデュッセイア型、ある時代や国そのものが主人公となっているのはイリアス型、というものだが、これを読んでわたしは、初めてこの世界文学最初期の二冊を手に取る気になったのだった。ホメロスを一読すると、シェイクスピアの『トロイラスとクレシダ』のようにギリシア神話を題材にした文学や、ユマニスムの時代の作品を読むのが一気に楽しくなる。なんだかんだまだ読んでないや、というひとは、ぜひ手にとってみてほしい。その後の読書人生を大きく変える、一生忘れられない読書体験になるだろう。
033.アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
Antoine de Saint-Exupéry(1900-1944)
『南方郵便機』(Courrier Sud, 1929)、『夜間飛行』(Vol de Nuit, 1931)、『星の王子さま』(Le Petit Prince, 1943)
『星の王子さま』は普段本を読まないひとだって知っているほど有名な作品だが、じつはその影に隠れた『夜間飛行』は、今後もう二度と期待できないであろうほどに完成度の高い長篇小説である。長篇と呼んだが、じつは文庫本でもたかだか100ページのごく短い作品で、その密度、表現の美しさは、まさしく「影のなかのひとつ星」である。いつでも気安く手を出せる長さなので、もう何度読んだことかわからないほどだ。ロバート・ウェストールの『ブラッカムの爆撃機』やロアルド・ダールの『飛行士たちの話』と並んで、宮崎駿の偏愛でも知られる一冊。
「ただ、今は、太陽が生きているはずの東方を見つめたところでなんの役にも立たなかった。彼と太陽のあいだには、誰にも這い上がることのできないほどの夜の深さが横たわっていた」(『夜間飛行』76ページ)
032.アドルフォ・ビオイ=カサーレス
Adolfo Bioy-Casares(1914-1999)
『モレルの発明』(La invención de Morel, 1940)
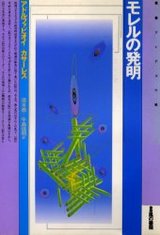
- 作者: アドルフォビオイ・カサーレス,清水徹,牛島信明
- 出版社/メーカー: 書肆風の薔薇
- 発売日: 1990/09
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 10回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
ボルヘスを除いて、ラテンアメリカは一人でいい、という乱暴な考えがもともとあった。となると、わたしの偏見が選び出すのは当然カサーレスである。ガルシア=マルケスも『エレンディラ』や『百年の孤独』を読んではいるが、『モレルの発明』ほどの興奮を与えてはくれなかった。この本はわたしに『独身者の機械』という現代の神話を伝える本を教えてくれた一冊で、わたしの読書の幅を飛躍的に広げてくれたものでもある。「マジック・リアリズム」という言葉で括られがちな南米作家たちの作風などどこ吹く風といった態で、チェスタトンの『木曜日だった男』やスティーヴンスンの『新アラビア夜話』といった怪奇小説にかぎりなく近い。これらの作品が好きな方は、南米にまったく興味がなくってもぜひ手にとってみてほしい。
「いまや私の未来にあるのは、涙と自殺のみだ」(『モレルの発明』164ページ)
031.ルイ=フェルディナン・セリーヌ
Louis-Ferdinand Céline(1894-1961)
『夜の果てへの旅』(Voyage au bout de la nuit, 1932)

- 作者: セリーヌ,Louis‐Ferdinand C´eline,生田耕作
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2003/12
- メディア: 文庫
- 購入: 11人 クリック: 224回
- この商品を含むブログ (73件) を見る
避けて通れるのなら絶対に避けたい危険地帯、それがセリーヌである。以前友人が書いていた言葉を引用しよう。「死にたくなるので、こんな本読まないほうがいいです。もう手遅れなら必読」。わたしはいまでも、これほど端的なセリーヌ評はないと思っている。『夜の果てへの旅』一作を読んだきりだが、『卑怯者の天国』などで生田耕作が翻訳をぼろくそに言った『なしくずしの死』などは、きっと永遠に手に取らないだろう。もともとフランス語でも読みやすいわけでもないので、苦行になることは必至である。できれば二度と読みたいとは思わずに生きたい。
「たとえ奴らが七億九千五百万人で、僕のほうは一人ぼっちでも、間違っているのは奴らの方さ」(『夜の果てへの旅』上巻、105ページ)
030.アーネスト・ヘミングウェイ
Ernest Hemingway(1899-1961)
『武器よさらば』(A Farewell to Arms, 1929)、『老人と海』(The Old Man and the Sea, 1952))、『移動祝祭日』(A Moveable Feast, 1964)
『移動祝祭日』のあまりのすばらしさが、それほどおもしろいと思ったわけでもない彼のほかの著作さえも、好感の持てるものにしている。死後出版された1920年代パリの回想録は、小説ではないが、彼の最高傑作である。「雑記:移動祝祭日記」でも紹介したことがあるが、シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店はいまもパリにあり、この記念碑的本によって文学好きのための巡礼の地と化した。2009年に未発表原稿を含む新編集版が出たので、高見浩氏が翻訳してくれないかなあ、と願っている。チャンドラーの『さらば愛しき女よ』やアデアの『閉じた本』、キャパの『ちょっとピンぼけ』など、皮肉った調子でヘミングウェイの名が話題になる文学作品は数多いが、そのことはこの作家がどれほど愛されているかを雄弁に語っているように思う。
「いまの時代にいちばん欠けているのは、野心をまったく持たない書き手と、本当に素晴らしい、埋もれたままの詩だと思うんだ。もちろん、どうやって暮らしていくかという問題もあるけどさ」(『移動祝祭日』203ページ)
029.レーモン・ルーセル
Raymond Roussel(1877-1933)
『アフリカの印象』(Impressions d'Afrique, 1910)、『ロクス・ソルス』(Locus Solus, 1914)、評伝:岡谷公二『レーモン・ルーセルの謎』(1998)

- 作者: レーモンルーセル,Raymond Roussel,岡谷公二
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2004/08
- メディア: 新書
- 購入: 8人 クリック: 96回
- この商品を含むブログ (76件) を見る
機械の説明書を読むのが好きなひとにうってつけの作家、それがレーモン・ルーセルである。とはいえ『アフリカの印象』を先に手にとったりすると、まずまちがいなく読み終えることができないと思うので、この作家に関してだけは、四の五の言わずに『ロクス・ソルス』から読んでもらいたい。アンドレ・ブルトンの最高の功績は、放っておいたらまちがいなく消えたこの作家の名を歴史に刻みつけたことだろう。「狂人の打ち明け話」という言葉に、これほど合致した作家もいない。カサーレスの『モレルの発明』などとあわせて読むと、「独身者の機械」という現代の神話の扉が開かれる。詳細はカルージュの同名の著書『独身者の機械』を参照されたい。新訳が刊行されたことをひっそり喜んでいる。
「先生は、天気予報術を、その可能の限界ぎりぎりまで押し進めていた。感度が抜群で、正確な沢山の器具による調査のおかげで、彼は、一定の場所におけるすべての風の向きも強さも、どんな小さな雲の発生も、大きさも、厚さも、凝縮の可能性も、十日前に知ることができた。彼は、その予測がいかに完璧であるかを誇示するため、太陽と風の働きを組み合わせるだけで美的作品を創造することのできる装置を考案した」(『ロクス・ソルス』45~46ページ)
028.ジャック・ルーボー
Jacques Roubaud(1932-)
『麗しのオルタンス』(La Belle Hortense, 1985)

- 作者: ジャックルーボー,Jacques Roubaud,高橋啓
- 出版社/メーカー: 東京創元社
- 発売日: 2009/01/28
- メディア: 文庫
- 購入: 7人 クリック: 166回
- この商品を含むブログ (46件) を見る
創元推理文庫に収められた『麗しのオルタンス』は、もはやその存在自体が冗談である。いったい誰がこれをミステリーとして読むのか、編集者の胸ぐらを掴んで問いただしたいほどだ。ついでにどうして続編を刊行しないのか、猫なで声で尋ねることも忘れないようにしよう。フランス語で読もうとしたことがあるのだが、もちろん生易しいものではなかったのだ。ちなみに水声社が刊行した『ジャック・ルーボーの極私的東京案内』は、わたしは原書でしか読んでいないが、日本のこと(おもにウォシュレットの機構)を描いた大変愉快な書物である。もっと翻訳されるべき作家の筆頭だ。
「お嬢さん、あなたの目は美しい、とくに右目が」(『麗しのオルタンス』99ページ)
027.アルベール・カミュ
Albert Camus(1913-1960)
『L'étranger』(1942)、『転落』(La Chute, 1956)

L'Etranger (Collection Folio, 2)
- 作者: Albert Camus
- 出版社/メーカー: Gallimard
- 発売日: 1990/10
- メディア: マスマーケット
- 購入: 2人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
カミュは哲学者としての知名度の高さから大変難解な作家と思われがちだが、その小説はものによっては徹底して読みやすく、じつは『異邦人』は、わたしの拙いフランス語力でもすいすい読めてしまうほどだ。作品ごとにその姿をがらりと変える様は、カルヴィーノにも通じているように思え、『嘔吐』を読んでみて思ったが、同じ「実存主義の徒」として語られがちなサルトルよりも圧倒的におもしろい小説を書く。もちろん哲学者としてもすばらしく、『シーシュポスの神話』など、何度読んでも読み終えた気にならない。カミュの作品とは、いつまでも親しく付き合っていきたいと思っている。ただ、『幸福な死』だけはもう二度と読みたくない。
「彼はまだ私に神様の話をしたがったが、私は彼の前に進み出て最後にもう一度説明を試みた。つまり、私にはもう僅かな時間しか残されておらず、それを神様などと一緒に浪費するつもりはないということを」(『L'étranger』180ページ)
026.ロラン・バルト
Roland Barthes(1915-1980)
『零度のエクリチュール』(Le Degré zéro de l'écriture, 1953)、『明るい部屋』(La Chambre claire, 1980)

- 作者: ロランバルト,Roland Barthes,花輪光
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1997/06
- メディア: 単行本
- 購入: 8人 クリック: 95回
- この商品を含むブログ (123件) を見る
バルトの名がこんなところにあるのはわれながらちょっとおかしいと思うのだが、わたしにとって『零度のエクリチュール』は稀代の冒険小説であり、『明るい部屋』は含蓄ある最高のエッセイなのである。考え方そのものをこれほど揺さぶる作家はそうおらず、「エクリチュール」や「プンクトゥム」という言葉を導入することでどんなに多くのことが語れるようになるかは驚くばかりだ。だからこれは、専門用語が大嫌いなわたしにとっても、「必要なペダンティスム」なのだと頷ける。そのややこしい文章をときどき無性に読みたくなるのだが、この事実がすでに、この作家の揺るぎない価値を高らかに告げている。
「私が名指すことのできるものは、事実上、私を突き刺すことができないのだ。名指すことができないということは、乱れを示す良い徴候である」(『明るい部屋』65ページ)
025.マルセル・プルースト
Marcel Proust(1871-1922)
『失われた時を求めて』(A la Recherche du Temps Perdu, 1913-1927)

失われた時を求めて〈1〉第一篇「スワン家のほうへ1」 (光文社古典新訳文庫)
- 作者: マルセルプルースト,Marcel Proust,高遠弘美
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2010/09/09
- メディア: 文庫
- 購入: 8人 クリック: 67回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
記事を一度も書いたことがないのに、ここに名前を連ねたのはプルーストとブローティガンだけだ。初めに断っておかねばならないが、わたしは『失われた時を求めて』をまだ読み終えていない。前に『スワン家の方へ』を記事にしようとしたことがあるのだが、引用好きなわたしのこと、本を丸々書き写してしまいたくなり、結局そこで記事にするのは諦めてしまった。プルーストを読む感覚は日記や書簡集を読むときのそれに近く、読者は小説のストーリーを追うというより、黄金探索者としてマドレーヌが呼び起こす記憶に耽溺していくのだ。しかもそこは金しか出てこない炭鉱なので、気軽に引き返すこともできなくなり、それについて何かを書こうとしても、形容よりも先にそこで見たものが口をついて出てき、それは自分の言葉じゃないと気づいて途端に沈黙する、といった具合である。鈴木道彦訳は研究者向きというか、ひとつひとつの訳は正確なのだろうけれど、すいすい読むには不向きなので、光文社古典新訳文庫の高遠弘美訳で最初から読み直したいと考えている。良いものは何度読んでも良い。
024.フランツ・カフカ
Franz Kafka(1883-1924)
『流刑地にて』(In der Strafkolonie, 1919)

- 作者: フランツカフカ,Franz Kafka,池内紀
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2006/07
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
カフカを読んだのはずいぶん前のことなので、『独身者の機械』がらみの関心で手にとった『流刑地にて』しか記事がないという傍目にもおかしなことになってしまっている。池内紀訳の白水社の全集をぜんぶ読みたいと常々思っているのだが、なんだか始める機会をずっと逸してしまっているのだ。『変身』を読んだのすらもうずっと前のことなので、まずはその再読から始め、ゆくゆくはまだ一度も読んだことがない『失踪者』などにまで手を伸ばしたいと思っている。
023.ルイス・キャロル
Lewis Carroll(1832-1898)
『不思議の国のアリス』(Alice's Adventures in Wonderland, 1865)、『鏡の国のアリス』(Through the Looking-Glass, 1871)、『スナーク狩り』(The Hunting of the Snark, 1876)

- 作者: ルイス・キャロル,河合祥一郎,ヘンリー・ホリデイ,高橋康也
- 出版社/メーカー: 新書館
- 発売日: 2007/07/24
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 8回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
世紀のロリコンとしてその名を燦然と轟かせるルイス・キャロルは、わたしにとっては『スナーク狩り』で不動の地位を得た作家である。突っ込みがないのにボケだけが延々と続くような破綻した作品で、彼がなにをしたかったのか、読み終えてもさっぱりわからない。つい最近穂村弘の翻訳が刊行されたので、再読のきっかけを与えてもらったように感じている。ちなみにこの本をフランス語に訳したのは、ウリポのメンバー、ジャック・ルーボーである。
「ここじゃみんな気が狂ってるんだ。わたしも気ちがい、あんたも気ちがい」(『不思議の国のアリス』106~107ページ)
022.レイ・ブラッドベリ
Ray Bradbury(1920-2012)
『火星年代記』(The Martian Chronicles, 1950)、『華氏451度』(Fahrenheit 451, 1953)
ブラッドベリと言えば、小笠原豊樹が訳した『火星年代記』が最初に思い浮かぶ。もっとよほど有名なはずの『華氏451度』の名を知るよりも前に自分がこの本を手に取ったのは、いったいどういう運命の巡り合わせだったのだろう、と思わずにはいられない。これまでに読んだ二冊があれほどすばらしかったのに、それ以降ぜんぜんこの作家の本を手にとっていない理由もわからない。わたしは小笠原豊樹が訳した本は死ぬまでにすべて読みたいと思っているので、短篇集の『太陽の黄金の林檎』や『刺青の男』、長篇『死ぬときはひとりぼっち』なども、近々手に取りたいと考えている。
「考える人間なんか存在させてはならん。本を読む人間は、いつ、どのようなことを考えだすかわからんからだ。そんなやつらを、一分間も野放しにおくのは、危険きわまりないことじゃないか」(『華氏451度』101ページ)
021.イタロ・カルヴィーノ
Italo Calvino(1923-1985)
『不在の騎士』(Il Cavaliere Inesistente, 1959)、『冬の夜ひとりの旅人が』(Se Una Notte D'Inverno Un Viaggiatore, 1979)

- 作者: イタロカルヴィーノ,Italo Calvino,脇功
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1995/10
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 22回
- この商品を含むブログ (51件) を見る
カルヴィーノほど作品によって姿を変える作家はほかに見たことがなく、十の作品を読めば十のカルヴィーノと出会うことになる。以前『アメリカ講義』を読んだのだが、書きたいことがあまりにも多すぎて、結局記事にできないままでいる。『見えない都市』を読んだときにも同じことが起こった。どんなに言葉を費やしても、この超多面体の作家に対しては、一面的であることから逃れられないのだ。かなり前に書いた『冬の夜ひとりの旅人が』や『不在の騎士』の記事が、そのことを端的に表しているように思えてならない。メルヴィルの『バートルビー』的な失書症は、こういう作家を前にしたときに生じるのだと思う。
「二人称での話し方が小説になるためには彼や彼女や彼らといった呼称の群れから離れた、はっきりと区別され、また共存するふたつのあなたが少なくとも必要なのだ」(『冬の夜ひとりの旅人が』205ページ)
020.ヴァレリー・ラルボー
Valery Larbaud(1881-1957)
『罰せられざる悪徳・読書』(Ce vice impuni, la lecture, 1925)

- 作者: ヴァレリーラルボー,Valery Larbaud,岩崎力
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1998/09
- メディア: 単行本
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
このブログの名前は「Riche Amateur」だが、これは『罰せられざる悪徳・読書』からとった、わたしが目指す愛書家としての姿勢である。専門家めいたことはひとつも言わず、いつまでもただの愛好家として読書を楽しみ、そしてそれによって豊かになりたいのだ。この本の原書は英米文学の批評も含んだ分厚いもので、そちらをちまちま読んでいるうちに『A・O・バルナブース全集』が文庫化されるという大事件が起こった。みすず書房の版はきっと、かつてアヴリーヌ書房から刊行されていた薄い本を底本にしているのだろう(詳細は「雑記:愛書家双書について」を参照)。1920年代のパリの豊かさを告げる、どこまでも謙虚な作家である。
「秀れた作品がひろく知られるまでには普通長い時間がかかるものだし、どんな時代をとってみても、もっとも秀れた作家ともっとも有名な作家が一致することはない」(『罰せられざる悪徳・読書』15~16ページ)
019.デジデリウス・エラスムス
Desiderius Erasmus(1466-1536)
『痴愚神礼讃』(Morias enkomion, 1511)

- 作者: エラスムス,Desiderius Erasmus,渡辺一夫,二宮敬
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2006/09
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 18回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
エラスムスはわたしに「ユマニスム」という運動(傾向?)の魅力を教えてくれた張本人であり、今回のランキングでは彼を入れたのでモンテーニュ(『エセー』)とペトラルカ(『ルネサンス書簡集』)は割愛した。およそ300年間の文学をたったひとりに代表させるというのだからこれほどの暴挙もないが、エラスムスにはそれだけの包容力があると思うのだ。このひとの『痴愚神礼讃』や割愛した二人の作品を読まなかったら、たとえばルキアノスの『遊女の対話』や、ルクレティウスの『物の本質について』などを手に取ることはけっしてなかったであろう。平易な言葉で賢人や老人たちをこき下ろした『痴愚神礼讃』は大変愉快な書物で、小難しいことを考えずにユーモア文学として読んでも、とびきりの笑いを提供してくれる一級品である。
「なにがおもしろいと申しても、地獄から戻ってきたのではないかと思われるような屍同然の梅干し婆さんたちが、口を開けば、「人生は楽しいわ!」などと繰り返すのを拝見することくらいおもしろいことはありません。こういう婆様連中は、牝犬同様にほかほかしておられまして、ギリシア人たちがよく申すとおり、「山羊の匂い」がいたしますよ」(『痴愚神礼讃』88~89ページ)
018.ジョルジュ・バタイユ
Georges Bataille(1897-1962)
『マダム・エドワルダ/目玉の話』(Histoire de l'œil, 1928. Madame Edwarda, 1941)、『空の青み』(Le Bleu du ciel, 1957)、『死者』(Le Mort, 1967)
バタイユは大変難解な作家として知られているので、わざわざ好きだなどと書くと、恰好つけているようでちょっと恰好悪い。だが、わたしが好きなバタイユは難解な哲学者ではなく、ロマンティックな小説家としての彼なのである。「あんなエロ本のどこがロマンティックなのさ?」と尋ねられるかもしれないが、エロティックであることとロマンティックであることとは矛盾しない。小説がこのうえなくエロティックであり、同時にロマンティックでもありえるということを証明したのが『空の青み』である。われわれは肉体関係さえ結べばロマンティックな関係が終わりを告げると考えがちだが、その「事後」からはじまるロマンだってあるのだ。『黒い美術館』のマンディアルグや『フロッシー』のスウィンバーンなども、それを描く地点にまでは到達できなかったように思える。ただバタイユだけが、エロスの向こう側にいる。
「彼女の舌が私の舌を求めて来たとき、あまりの美しさに私はもう生きていたくなかった」(『空の青み』225ページ)
017.ジェイムズ・ジョイス
James Joyce(1882-1941)
『若い藝術家の肖像』(A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916)

- 作者: ジェイムズジョイス,James Augustine Aloysius Joyce,丸谷才一
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2014/07/18
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る
主人公の成長を描いた長篇小説はいくらでもあるが、その成長とともに小説の言葉遣いまでめまぐるしく変わるのは、わたしの知るかぎり『若い藝術家の肖像』だけだ。『ユリシーズ』はまだその時期ではないと考え、一度読破を諦めたままその後手にとっていないわたしではあるが、ジョイスがいかに風変わりで偉大な作家であるかは、『若い藝術家の肖像』を読むだけでも十分にわかる。これほど爽快な読後感を与えてくれる長篇小説はそうそうなく、主人公のスティーヴン・ディーダラスが『ユリシーズ』にも登場しているのが信じられないくらいだ。丸谷才一の渾身の訳業がめでたくも文庫化されたので、読まなきゃと思いつつもまだ手にとったことがなかったようなひとには、ぜひともこの圧倒的な読書を体験してみてほしい。圧倒的。これほどジョイスにうってつけの形容詞もない。
「ぼくは自分が信じてないものに仕えることをしない。家庭だろうと、祖国だろうと、教会だろうと。ぼくはできるだけ自由に、そしてできるだけ全体的に、人生のある様式で、それとも藝術のある様式で、自分を表現しようとするつもりだ。自分を守るためのたった一つの武器として、沈黙と流寓とそれから狡智を使って」(『若い藝術家の肖像』454ページ)
016.リチャード・ブローティガン
Richard Brautigan(1935-1984)
『アメリカの鱒釣り』(Trout Fishing in America, 1967)、『芝生の復讐』(Revenge of the Lawn, 1971)、『愛のゆくえ』(The Abortion, 1971)
わたしがブログの更新をやめたのは、ちょうどブローティガンを読んでいたころだ。この圧倒的な詩情を前にして、書く理由が浮かばなくなってしまったのだ。わたしは読書の最中、気に入った文章のあるページの端を折るのだが、ブローティガンの本は一ページに何度も、というかページのほとんどすべてが「気に入った文章」で構成されているため、大変なことになった。『芝生の復讐』をどんなに愛しているか、どれほど言葉を費やしても伝えられる気がしない。『愛のゆくえ』がどれほど特別な存在か、『アメリカの鱒釣り』がどんなに愉快か、それを説明できる言葉など、存在しないように思えてしまうのだ。この作家はプルーストと並んで、いつまでも記事にはできないように思っている。
015.ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
Johann Wolfgang von Goethe(1749-1832)
『若きウェルテルの悩み』(Die Leiden des jungen Werthers, 1774)、『ファウスト』(Faust, 1806, 1831)
ゲーテには昔、背伸びして無理やり『ファウスト』を読み、徹底的に打ちのめされた苦い思い出があり(とくに第二部!)、無理してページを繰り続けることの無意味さを教えてもらった。その後『若きウェルテルの悩み』を読んでみたら、難解さなどは欠片もなく、一気に身近な存在になった。若者の絶望に包まれたこの作品はラディゲの『肉体の悪魔』同様、多感な時期に読んでこそ本領を発揮する、不朽の名作である。できれば十代のうちに出会っておきたかった。
「ウィルヘルム、はっきりいうよ、ぼくは誓ったんだ、ぼくが愛し求めているひとにはぼく以外の誰ともワルツは踊らせない、たといそのためにぼくの身が破滅しようとも」(『若きウェルテルの悩み』32~33ページ)
014.レイモンド・チャンドラー
Raymond Chandler(1888-1959)
『さらば愛しき女よ』(Farewell, My Lovely, 1940)、『高い窓』(The High Window, 1942)、『湖中の女』(The Lady in the Lake, 1943)、『長いお別れ』(The Long Goodbye, 1953)

さらば愛しき女よ (ハヤカワ・ミステリ文庫 (HM 7-2))
- 作者: レイモンド・チャンドラー,清水俊二
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 1976/04
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 29回
- この商品を含むブログ (89件) を見る
チャンドラーの文章はシェイクスピアと同じくらい引用されてもいい。もちろん、小説と戯曲という表現形式のちがいはあるが、戯曲がちょうど詩のように高密度な表現を織り込むのに適した形式であるのに対して、チャンドラーはそれを小説でやってしまったのだ。それも、探偵小説で! この事実はもうちょっと考えられるべきだと思う。『長いお別れ』がとくに有名だが、わたしが声を大にして愛を表明したいのは、『さらば愛しき女よ』だ。
「「君の態度が気に入らんね」と、キングズリーはアーモンドの果を砕いてしまいそうな声でいった。
「かまいません」と、私がいった。「そいつを売ってるわけではないんで」」(『湖中の女』10ページ)
013.E・M・フォースター
Edward Morgan Forster(1879-1970)
『天使も踏むを恐れるところ』(Where Angels Fear to Tread, 1905)、『アレクサンドリア』(Alexandria, 1922)

天使も踏むを恐れるところ (白水Uブックス―海外小説の誘惑)
- 作者: E.M.フォースター,E.M. Forster,中野康司
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1996/08
- メディア: 新書
- クリック: 9回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
フォースターに対するわたしの愛は、アナトール・フランスに対するそれにかぎりなく近い。同時代人のジョイスやウルフとは異なり、新しい文学形式をまるで追究せず、ただ完成された小説を書こうとしたその謙虚な姿勢に、ただならぬ好感を抱いているのだ。吉田健一訳の『ハワーズ・エンド』が有名だが、原書と照らしてみたとき、同じ小説と思えないのはどうなのよ、と思う。わたしが読みたいのはもっと純粋なフォースターなのであり、だからいまでも『天使も踏むを恐れるところ』ほどにわたしを喜ばせてくれる翻訳はないのだ。みすず書房が刊行していた「著作集」には中野康司の翻訳も数多く含まれているので、次に日本に帰ったときには、問答無用で全巻揃えてしまおうと考えている。
「イギリスにもこういう菫はあるけれど、こんなにたくさんは咲いていない。絵のなかでも、こんなにたくさんは咲いていない。こんなにたくさんの菫を咲かせる勇気のある画家はいないからだ」(『天使も踏むを恐れるところ』29ページ)
012.ジャック・プレヴェール
Jacques Prévert(1900-1977)
『プレヴェール詩集』(編纂)
プレヴェールにはかつて複数の訳書があったのに、いまは軒並み絶版になってしまっている。『ルネサンス書簡集』のペトラルカにならって、こう言いたい。「私には大きな悲しみであり、現代にとっては大きな恥辱、後世にたいしては大きな不正です」。わたしが復刊してもらいたいのはもちろん小笠原豊樹の訳書であり、これは「ときどき」、フランス語原文で読むよりもうつくしい。プレヴェールが気軽に手に取れない世の中というのは、ただただまちがっている。
「天にましますわれらの父よ
天にとどまりたまえ
われらは地上にのこります
地上はときどきうつくしい」
(「われらの父よ」より、『プレヴェール詩集』13~15ページ)
011.ホルヘ・ルイス・ボルヘス
Jorge Luis Borges(1899-1986)
『伝奇集』(Ficciones, 1935-1944)、『創造者』(El hacedor, 1960)

- 作者: J.L.ボルヘス,Jorge Luis Borges,鼓直
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2009/06/16
- メディア: 文庫
- 購入: 5人 クリック: 27回
- この商品を含むブログ (47件) を見る
ボルヘスの明晰さはわたしにとってはヴァレリーに通じるものがあり、詩なのか小説なのか判別しがたい作風もすこし似ているような気がしている。どちらもページを開く前には深呼吸が必要で、開けばいつも期待以上のものをもたらしてくれるところまでそっくりだ。ところで、彼を「マジック・リアリズム」の作家と呼ぶのはまちがっていると思うのだが、いかがだろうか。ただラテンアメリカの作家というだけで、たとえばガルシア=マルケスとの共通点など、ひとつもないと思う。チェスタトンやスティーヴンスンを愛してやまない姿勢も、とても好きだ。評論を書いても抜群の知性を発揮する作家として、ボルヘス、ヴァレリー、カルヴィーノの三人は、わたしのなかで不動の地位を占めている。
「率直に言って覚えていないのだ、あの晩、実際に自殺をしたのかどうか」(「ある会話についての会話」より、『創造者』23ページ)
010.ギュスターヴ・フロベール
Gustave Flaubert(1821-1880)
「愛書狂」(Bibliomanie, 1836)、『ボヴァリー夫人』(Madame Bovary, 1857)、『感情教育』(L'Éducation sentimentale, 1869)

- 作者: ギュスターヴ・フローベール,山田ジャク
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2009/09/04
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
小説という文学形式はわたしたちが体感しているよりもずっと歴史の浅いものであるが、これは19世紀のフロベールによって、早々と完成されてしまったのだと信じて疑わない。フロベール以降、『居酒屋』のゾラやモーパッサン(彼は『Apparition』のような短篇のほうが巧みだが)といった直接的な継承者を経て、やがて今度は間接的な継承者であるアナトール・フランスらを否定するかたちで、シュルレアリスムのような文学運動が組織される。こういった歴史すべてが、フロベールがあそこまで完成度の高い作品を書かなかったら、起こらなかったことのように思えてならないのだ。新たな『感情教育』を書くことがひとつの理想であった時代から、『感情教育』からできるだけ距離を置くことが目標とされる時代になった。ただ、それを意識するあまり、現代の文学は窒息してしまっているようにも思えるのだ。もちろんウリポのような幸福な例外もあるが、現代において「ポストモダン文学」を自称するようなすべての作家は、いまでもわたしには縁遠い。わたしが読みたいのは、新たな『感情教育』のほうなのだから。
「くそ、もううんざりだよ。ロベスピエールの断頭台、皇帝ナポレオンの長靴、ルイ=フィリップの雨傘と、つぎからつぎへ何にでも平伏するやつら、パンを投げ与えてくれる者ならだれにでもいつだって忠誠を誓う卑しいやつらにはうんざりだよ! タレイランやミラボーは、金で動いたからといっていつも声高にやっつけられるが、なに、下の階の使い走りの便利屋ね、あいつなんかに一回の使い走り三フランの値でもつけてやりゃあ、五十サンチームで国を売ることぐらい朝飯前だろうよ。ああ、大間違いだったんだ! われわれはヨーロッパ全土に火をかけてしまうべきだったんだよ!」(『感情教育』下巻、239ページ)
009.ウィリアム・シェイクスピア
William Shakespeare(1564-1616)
『ロミオとジュリエット』(Romeo and Juliet, 1595-1596)、『お気に召すまま』(As You Like It, 1599)、『ハムレット』(Hamlet, 1600-1601)、『トロイラスとクレシダ』(Troilus and Cressida, 1601-1602)、『リア王』(King Lear, 1605)、『マクベス』(Macbeth, 1606)

シェイクスピア全集 (〔23〕) (白水Uブックス (23))
- 作者: ウィリアム・シェイクスピア,小田島雄志
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1983/01
- メディア: 新書
- 購入: 7人 クリック: 74回
- この商品を含むブログ (18件) を見る
シェイクスピアほど愉快な作家はそうそういないのだが、あまりのビッグネームぶりに腰が引けてしまうひとも多いように思える。たしかに、新潮文庫の福田恒存訳などを読んでいたらそう思ってしまうのも無理はないのだが、白水社の小田嶋雄志訳はそんな風潮に高らかに異を唱える名訳揃いの一級品である。われわれがシェイクスピアを読むのは教養を得るためではなく、もちろんあらすじを確認するためでもなく、読んだことをだれかにひけらかすためでもない。ただ、楽しむために読むのだ。『ロミオとジュリエット』で繰り広げられる、ロミオとその友人マキューシオの応酬を読めば、これがどんなに愉快な本であるか、きっと理解してもらえるだろう。一面的な悲劇のイメージなど、この読書体験の前ではなんの意味もない。わたしにとっての最高の休日の過ごし方はいまでも、公園に一日中寝そべってシェイクスピアの一作を読みきってしまうことだ。
「この世界で私はただ一人分の場所をふさいでいるだけの男です、私がそこをどけばもっとましな人間があとを埋めてくれるでしょう」(『お気に召すまま』26ページ)
008.アントン・チェーホフ
Anton Chekhov (Tchekhov)(1860-1904)
『かもめ・ワーニャ伯父さん』(Чайка, 1896. Дядя Ваня, 1899-1900)、『桜の園・三人姉妹』(Три сестры, 1901. Вишнёвый сад, 1904)、『かわいい女・犬を連れた奥さん』(編纂)、『カシタンカ・ねむい』(編纂)
チェーホフはもちろん劇作家として有名だが、近年稀代の短篇小説作家としてもスポットライトを当てられるようになっていて、勝手に喜んでいる。初めてわたしにその短篇の魅力を教えてくれたのは小笠原豊樹訳の『かわいい女・犬を連れた奥さん』で、その後『すばる』だかなにかの文芸誌で井上ひさしが「コントラバス物語」という作品を紹介しており、そのあまりの魅力に、勢いで全集を揃えてしまった。大変翻訳者に恵まれた作家という印象もあり、神西清による『カシタンカ・ねむい』もすばらしい作品集である。ちなみに「コントラバス物語」は中央公論社版全集の第5巻に収められているので、古本屋や図書館で見かけたときにはちょっと読んでみてほしい。
「本当にあなたは、男じゃなくて、まるでお粥みたいだわ。男っていうものは、夢中になったり、気狂いみたいになったり、過ちをしたり、苦しんだりするものだわ。あなたが無作法をしたり図々しい事をしても女は許すけど、小利口なのは許さないものよ」(「アリアドナ」より、『カシタンカ・ねむい』172~173ページ)
007.フェルナンド・ペソア
Fernando Pessoa(1888-1935)
『不穏の書、断章』(extracts from O Livro do desassossego, 1982)
ペソアはぼくらのアイドルである。幾通りものペンネームは、彼がどれほどの社会不適合者であったかを告げているかのようだ。現代において詩人である以外の選択肢がひとつもない人生というのがいかなるものか、この詩人はひっそりと教えてくれる。『不穏の書、断章』は四六時中、肌身離さず持っていたい。
「文学は、他の芸術と同様、人生がそれだけでは十分でないことの告白である」(『不穏の書、断章』13ページ)
006.G・K・チェスタトン
Gilbert Keith Chesterton(1874-1936)
『新ナポレオン奇譚』(The Napoleon of Notting Hill, 1904)、『木曜日だった男』(The Man Who Was Thursday, 1908)
『木曜日だった男』の完璧さはいまだに忘れがたく、それこそボルヘスがカサーレスの『モレルの発明』を評したのと同じ口調で「これは完璧な小説である」と言いたい。しかも、これら二作品はどこかすこし似てさえいるのである。どこを切り取っても美しく、そのうえ余分なものなどなにひとつないように思えるのだ。「こんなにおもしろい小説はじめて読んだ」と言う権利を、『木曜日だった男』を読んでしまったことで、わたしは永遠に失った。「ブラウン神父」の探偵小説シリーズが南條竹則訳で刊行されはじめたのは大事件なのだが、どういうわけか最初の『ブラウン神父の無心』以降、音沙汰がない。この本に収められた「秘密の庭」はミステリー好きなら絶対に読むべき、常識を覆す一篇だと思うのだが、いかがだろうか。期待している以上のものを必ず提供してくれる作家というのはそうそういるものではないので、もっとたくさんの本が気軽に手にとれるようになってもらいたいものだ。
「僕は酔ってないとしたら、狂ってるんだ。でも、そのどちらの状態でも紳士らしく振舞えるつもりだがね」(『木曜日だった男』35ページ)
005.P・G・ウッドハウス
Pelham Grenville Wodehouse(1881-1975)
『比類なきジーヴス』(The Inimitable Jeeves, 1923)、『エムズワース卿の受難録』(編纂)、『ユークリッジの商売道』(編纂)

- 作者: P.G.ウッドハウス,P.G. Wodehouse,岩永正勝,小山太一
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2008/12/15
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
ウッドハウスに対するわたしの偏愛は至るところで語っているが、この作家のすばらしさはいくら強調してもまだ足りないくらいだ。なにせ彼は、この偏見まみれのランキングによると、すでにシェイクスピアを超えてさえいるのである! いつ開いても腹がよじれるほどに笑わせてくれる文体というのは、もうそれ自体価値である。だから、本は正直もうなんでもよかったのだが、わたしがとくに好きなのは『ユークリッジの商売道』だ。単語が難しすぎてまだぜんぜん歯が立たないが、いつか英語原文でも読めるようになりたい。
「僕は部屋の隅にそっと避難し、新米の猛獣使いの心境を味わっていた。どうしたわけかライオンの檻に閉じ込められてしまい、こういう場合の対処法が書いてある通信教育の第三課を必死に思い出そうとしている心境だ」(『ユークリッジの商売道』351ページ)
004.アナトール・フランス
Anatole France(1844-1924)
『ジョカストとやせ猫』(Jocaste et le Chat maigre, 1879)、『シルヴェストル・ボナールの罪』(Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881)、『赤い百合』(Le Lys rouge, 1894)、『神々は渇く』(Les dieux ont soif, 1912)
アナトール・フランスに対するわたしの愛情はまさしく偏愛と呼ぶべきもので、どれくらい偏執的かというと、教育の行き届いたわたしのパソコンにひらがなで「あ」と入力するだけで、変換候補の筆頭に彼の名前が出てくるほどだ。普通はここまで評価される作家ではないような気がしている。フロベールより好きだと公言するだなんて! だが、その愛書家ぶりやユマニスムへの傾倒は、いくら愛を表明しても足りないくらいなのだ。『赤い百合』などは駄作と呼ばれても仕方がない長篇だが、アナトール・フランスを読むときのわたしは純粋な黄金探索者であり、つまりは美しい一文と出会うことだけを楽しみにしているので、文芸批評が話題にするような「物語の奥に隠されたもの」だとか、そういうものは心底どうでもいいのである。黄金探索者の目には、筋書きは陳腐な『赤い百合』でさえ、宝の山以外の何者でもないのだ。『神々は渇く』のブロト老は、ケストナーの『飛ぶ教室』に出てくる「禁煙さん」と並んで、あらゆる文学作品のなかで最も好きな登場人物である。
「「たくさんのご本でございますね。ボナール先生、先生はこれをみんなお読みになったのでございますか」
「悲しいことにみんな読みました。だからこそ何にも知らないのです。何しろどの本もほかの本と矛盾しないものは一冊もない、したがってみんなを知ればどう考えてよいかわからなくなる。私はそんな状態にいるのです」」(『シルヴェストル・ボナールの罪』185ページ)
003.ポール・ヴァレリー
Paul Valéry(1871-1945)
『ムッシュー・テスト』(La Soirée avec monsieur Teste, 1896. Monsieur Teste, 1926)、『エウパリノス・魂と舞踏・樹についての対話』(Eupalinos ou l'Architecte, 1921. L'Âme et la danse, 1923. Dialogue de l'arbre, 1943)、『書物雑感』(Notes sur le livre et les manuscrits, 1926)、『思考の表裏』(La Révolution Surréaliste N°12, 1929)、『ヴァレリー文学論』(編纂)、『ヴァレリー詩集』(編纂)

- 作者: ポールヴァレリー,Paul Val´ery,清水徹
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2004/04/16
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 27回
- この商品を含むブログ (43件) を見る
「読者を選ぶ」という表現は衒学的で嫌味に響くが、ヴァレリーほどこの言葉の似合うひともいない。しかも、わたしはまだ選ばれていない、という感覚さえあるのだ。ヴァレリーの明晰さは永遠の憧れであり、どんなに読んでも読み足りない。ヴァレリーを完全に理解できるなんて軽々しく公言するのは、完全な狂人か、ただの馬鹿だけである。ぜひ『ムッシュー・テスト』を読んで、打ちのめされてもらいたい。「わけわからん、つまらん」と言って、本を投げ出すひとがほとんどだと思うが、もしもあとになって、あなたがこの本をもう一度恐る恐る開くのなら、あなたはもうわたしの友人である。
「この水盤に、四十センチの深さがあろうと四千メートルの深さがあろうと、そんなことはどうでもよいのだ。僕らにうれしいのはその水の輝きだけだ」(『ヴァレリー文学論』82ページ)
002.エーリヒ・ケストナー
Erich Kästner(1899-1974)
『小さな男の子の旅』(Ein kleiner Junge unterwegs, 1927. Zwei Mutter und ein Kind, 1929)、『エーミールと探偵たち』(Emil und die Detektive, 1929)、『点子ちゃんとアントン』(Pünktchen und Anton, 1931)、『エーミールと三人のふたご』(Emil und die Drei Zwillinge, 1933)、『飛ぶ教室』(Das fliegende Klassenzimmer, 1933)、『雪の中の三人男』(Drei Männer im Schnee, 1934)、『一杯の珈琲から』(Der kleine Grenzverkehr, 1938)、『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen, 1949)
読者を泣かせるのは簡単だが、笑わせることは難しい。たしか『作文教室』だったと思うが、井上ひさしが語っていたことである。そして笑いにはいくつもの種類があるが、ウッドハウスのげらげらやチェーホフのにやりとは異なり、ケストナーは読者をにっこりさせる天才である。これほど後味の良い読書体験を提供しつづけてくれる作家はほかにおらず、彼の作品を読んだ途端、世界がそれまでよりも美しく見えるようになる。世の中に嫌気が差したとき、ほんとうに読むべきなのはケストナーなのだ。『飛ぶ教室』ほどわたしを泣かせ、同時に笑顔にもした作品はない。死ぬときには一緒に燃やしてほしいと、冗談ではなく思っている。
「金や、地位や、名誉なんて、子どもっぽいものじゃないか。おもちゃにすぎない。そんなもの、本物の大人なら相手にしない」(『飛ぶ教室』160ページ)
001.レーモン・クノー
Raymond Queneau(1903-1976)
『文体練習』(Exercices de Style, 1947)、『皆いつも女に甘すぎる』(On est toujours trop bon avec les femmes, 1947)、『サリー・マーラの日記』(Le Journal intime de Sally Mara, 1950)、『地下鉄のザジ』(Zazie dans le métro, 1959)、『サリー・マーラ全集』(Œuvres complètes de Sally Mara, 1962)、『イカロスの飛行』(Le Vol d'Icare, 1968)、『あなたまかせのお話』(Contes et propos, 1981)
一位はいつもどおりレーモン・クノーである。じつはもう、クノーが一位である必要はないとも思っているのだが、このひとほどわたしの人生を狂わせた作家はいないのだから仕方がない。わたしは、まだ水声社が「レーモン・クノーコレクション」の刊行をはじめる前、この作家の作品のほとんどが日本で翻訳されていないことを嘆き、フランス語を勉強しようと誓い、会社を辞めてフランスの大学に再入学したのだった。水声社のすばらしい仕事のおかげで、この経緯は笑い話になってしまったが、もちろん後悔などぜんぜんしていない。この作家がいるおかげで、いまのわたしはまがりなりにもフランス語を読むことができ、まだ知らない多数の作家と向き合うことが可能になっているのだ。クノーはもはやわたしにとっては、ただの作家であることを超えていて、特別な存在なのである。
「あたし、宇宙飛行士になって、火星人をしめあげるの」(『地下鉄のザジ』27ページ)
長かった。あまりにも疲れたので、できればまた三年くらいは更新したくない。こんなものを書いているがために読書時間が減ってしまうだなんて、本末転倒も甚だしい。しかしこうして見てみると、あらためて日本の翻訳出版のおそるべき豊富さが見てとれる。ここに挙げたほとんどすべての作品が日本語で読めるというのは、ちょっと奇跡としか言いようがないではないか。国際共通語であるはずの英語にだって、すべては訳されていないのだから。日本の翻訳出版の伝統は、世界に誇るべき快挙であると言い切っていいだろう。今日もまたどこかで、どこかの翻訳家の方が「未邦訳作品」と向き合っていると考えるだけでも、わたしの胸は躍る。
それでは皆さま、良いお年をお迎えください。来年もすてきな本と巡りあえますように。













































