ロシア・アヴァンギャルドと20世紀の美的革命
ブルース・チャトウィンの『どうして僕はこんなところに』に読みふけって以来、ずっと気になっていた「ロシア・アヴァンギャルド」と呼ばれる芸術運動について書かれた本。ロシア・アヴァンギャルドを芸術史上に位置づけた画期的な一冊。
ヴィーリ・ミリマノフ(桑野隆訳)『ロシア・アヴァンギャルドと20世紀の美的革命』未来社、2001年。
概説書としてはうってつけであるが、気軽に入門書と呼ぶには難解な記述も多い本である。1ページ読むのに10分以上かかるようなこともざらで、片手間に手に取ることは許されない、なかなか濃密な読書であった。はじめは翻訳が悪いのかと思いもしたのだが、そもそもの内容が簡単ではない。また、この未来社の訳書は奇抜な構成となっており、100点を超えるカラー図版は巻末にまとめられており、ときには「本文に入れろよ!」と突っ込みたくなるほど饒舌な原注と、グロイスという学者に対する批判に満ちあふれた、正直とても必要とは思えない「訳者あとがき」が、本文のあとにつづいている。本文、注、それから図版用に、しおりが3枚は必要になる本で、行ったり来たりを繰り返す必要が、読書のスピード感を奪っているのかもしれない。
この本のすばらしいところはその守備範囲の広さで、タイトルのとおり20世紀全体が対象となっている。最初の収穫は読み始めてすぐに現れた。「ポンピエ(pompier)」という言葉だ。これは19世紀のアカデミック絵画を揶揄した蔑称である。
「ノルデやキルヒナー、ゴンチャローヴァやラリオーノフ、シーレやココシュカは、ロダンの《考える人》ともクリムトの幻視的作品ともなんら共通点をもちあわせていない。双方のあいだには深淵があり、この深淵を目の前にすると、ロダンやクリムトの作品は、登場時にスキャンダルとなったわりには、古典的伝統の大陸に全面的に属していることが、一目瞭然である。これらは、見るものを心地よくさせてくれるブーグローその他の〈ポンピエ〉[十九世紀の作風が紋切り型の画家]の作品と同列におくことも、不可能ではない」(6~7ページ)
「ブーグローとジェロームの場合は死とともにその栄光も終焉を迎えたのにたいして、ゴーガン(1903)とセザンヌ(1906)の場合は、その死とともに作品の影響力や人気は増大の一方をたどっていく」(8ページ)
なぜこんなにも反応しているのかというと、わたしがいちばん好きな画家は、ここで名が挙げられているウィリアム・ブーグローなのだ。印象派や写実主義などが隆盛していくにつれ忘れ去られていった古典的作風の画家であり、その圧倒的技巧は17世紀フランドル絵画の細密描写と比してもすこしも見劣りしない、わたしにとっては究極の芸術である。絵画に造詣の深い友人に連れられ、初めてオルセー美術館の彼の作品の前に立たされたときの感動は忘れられない。

ブーグロー《二人の姉妹》(1901)
わたしの趣味はご覧のとおりなので、ロシア・アヴァンギャルドにお気に入りの画家がいるわけではもちろんない。正直、ぜんぜん好きにはなれない。むしろ、なぜこれほどまでに自分の趣味とかけ離れた絵画が存在しているのか、ということが興味の発端になっていると言えるくらいだ。そこにはブーグローらを否定するに至った心性、そこから発展していく印象派やキュビスムの形成、その影響を受けてさらに加速していく、まさしくロシア・アヴァンギャルドを構成したような人びとの姿がある。
興味深いのは、こういった過去の遺産を否定する流れが、各地で芸術運動のかたちをとって同時多発的に起こっていることだ。ブルトンの『シュルレアリスム宣言』が最初に公刊されたのは1924年のことである。思えばわたしの愛するアナトール・フランスは、彼らシュルレアリストたちによって死刑通告を放たれたのではなかったか。「新しい芸術の模索」のるつぼと化した1920年代のパリの興奮はヘミングウェイが『移動祝祭日』に書いているとおりだが、『ユリシーズ』によってその場の寵児となったジョイスよりも、同時代人でありながらもひっそりとオースティンに範を求めていたフォースターのほうに好感を抱くのは、わたしだけではないだろう。ジョイスも好きだけれど、20世紀に讃美されている理由からではない。これらはどんなに紙幅を割いても易々とは満足できない、非常に個人的でしかも広範な問題なので、別の機会にゆずろう。
さて、印象派やキュビスムの輸入は、ロシアにおいては個人蒐集家たちによってもたらされた。チャトウィンが紹介していたゲオルギー・コスタキのことが思い出される箇所である。だがその影響力については、わたしの想像をはるかに超えていた。
「こうした展覧会は、定期刊行物と同様、ロシアの芸術がヨーロッパの動きに加わるのに重要な役割を果たしたが、さらに大きな意味をもっていたのは、西欧の最新の芸術の個人コレクション――セルゲイ・シチューキンとイヴァン・モロゾフの有名な収集作品――であり、これはたえず補給されるとともに一般に公開されていた。結果にたいする評価はさまざまであるにせよ、この現象はみんなに歓迎されていた。トゥゲンホリドは、シチューキンの収集を「左翼芸術のアカデミー」と呼んでいる。ペトロフ=ヴォトキンは、モスクワを疫病のごとく埋め尽くす「最新のフランス絵画」に若者が「丸ごと影響されていく」様子を回顧して、「疫病はズナメンスキイ横町のシチューキン家からはじまった」と、より正確にいいかえている」(20ページ)
「これらのモスクワのコレクションが、1900年初年代から1910年代にかけてのモスクワの芸術界に起きた諸過程のもっとも重要な触媒であるとみなされているのも、もっともなことである。すでに当時よりいわれていたが、シチューキン・コレクションの補充は若い画家たちの作品にただちに影響を及ぼした。すなわち、コレクションが左傾化するにつれて、モスクワの画家たちも左傾化していった」(21ページ)
この本を読んだうえでチャトウィンを読み返してみると、コスタキ・コレクションが「最も活気にあふれた、世界最高の美術館」と評された裏には、こういった蒐集家による個人コレクション開陳の伝統があったことが明らかになってくる。その来客名簿の筆頭にストラヴィンスキーの名前があったのは象徴的だ。ストラヴィンスキーのバレエ音楽は興行師ディアギレフ(ここではジャーギレフ)によって、ロシアから見たときの「西欧」、すなわちフランスに紹介されたのだから。その成功がもたらした熱狂は、ロシア・アヴァンギャルドという運動を形成するのに十分なものだった。
「アナトール・フランスやメーテルランク、ロダン、ドビュッシー、ラヴェル、ロマン・ローランその他の多くの者たちが、芸術における新たな時代の始まりであると書いた、ジャーギレフの興行の大成功は、ロシアの新しい芸術に強力な刺激をあたえた」(25ページ)
「プリミティヴィズムへの転回において、すでに最初から、相異なり多くの点で対立する二種類の傾向が多かれ少なかれ区別される。片方は、(ルソー主義的な意味での)簡素化という理念を暗黙裏に抱いているものであり、〈プリミティヴ〉という概念に相応している。もう片方は、初期段階では区別しがたく、やはり一般化された非写実的な形態のなかにあらわれてはいるものの、目的は簡素化された形態それ自体にあり、形態の普遍化、形態の単純家にあった。前者の意味では、わが国のプリミティヴィズムは、ロシア的心性や、その農民的伝統の特質、ナロードそのものの神話化、簡素化のトルストイ的唱道などに由来している」(27ページ)
ロシア・アヴァンギャルドについて語るときには、マレーヴィチに目を向けるとおもしろい。その作風の変遷は運動そのものの縮図となっており、彼の作品を追うことでこの運動の発展していく図式をたどることができる。しかもそのまま追いつづけていくと、マレーヴィチはとんでもないところにたどり着くのだ。同じ画家の作品とは思えないほど、彼の作風はめまぐるしく変貌する。
「農民を描いた絵は、マレーヴィチの初期作品においてもきわだっている。ゴンチャローヴァの同種の作品と実際には区別しがたい作品(最初期の《水浴者》なども含む)が、1911年付けになっている。
しかし、すでに1912年の《刈り手》、《刈り取る女》その他になると、性格は明らかにまったく別のものになっている。アンスロポモルフィックな姿――手足、上半身と下半身――をつくりあげている抽象的な円筒の形態は、相互に取替えがきくかのようだ。卵型の頭、眼と眼のあいだ、鼻の両端も幾何学化されており、造形面からして彫刻的であり、組み立ては建築的であり、アンスロポモルフィックな儀礼的仮面のコンストラクションを再現している」(30ページ)

マレーヴィチ《刈り手》(1912)
この《刈り手》に見られた「交換可能な円筒」は、早くも翌年には驚くべき姿に変貌する。
「1913-14年にはマレーヴィチは模倣的システムの枠内からはじめて抜けでて、キュビスムや未来主義の絵画的構想を変奏し発展させており、そのことは《桶をかつぐ女》、《農民の娘の頭》その他の作品から見てとれる。たとえば《モスクワのイギリス人》、《飛行士》、《大ホテルの生活》、《モナ・リザのあるコンポジション》(すべて1914年)のような具象性がまだ十分保たれているような、この時期の作品においてすら、画家自身がのちに(論文「芸術における新しいシステムについて」のなかで)、ロシア的キュビスム独自の特徴とみなして〈アロギズム(非論理主義)〉という言葉で定義したような性質が増してきている。〈ザーウミ(超意味言語)〉やアロギズムは、破壊の用具であった。マレーヴィチの創造面での進化は、その理論的発言同様、伝統的な視覚の克服のほうが、新たな表象システムの創造以上に大きな緊張を要したことを証明している」(31~32ページ)

マレーヴィチ《桶をかつぐ女》(1912-13)
やがて彼が到達したのが、「スプレマチズム(Suprematism)」と呼ばれる抽象性である。これはもはや20世紀文学におけるバートルビー症候群、すなわち失書症に近いとさえ思える。
「はじめてスプレマチズム絵画をマレーヴィチが公開したのは、1915年秋にペトログラードで開催された「最後の未来派絵画展0.10」である。おなじ年に、かれの有名なマニフェスト小冊子『キュビスムからスプレマチズムへ』も出ており、それは「空間とは、理性がその創作を入れる、無次元の容器である。わたしは自分の創造的形態を入れたい」という言葉で切りだされていた」(32ページ)
「スプレマチズムという言葉の意味については解釈が分かれているが、わたしが直接に話をする機会のあったハルジエフは、マレーヴィチ自身を援用しつつ、この言葉の基礎になっているのは〈suprême〉ではなくて〈suprématies〉であると主張していた。前者の場合にはこの言葉は「絵画の最高段階」とみなすことになろうし、後者の場合は絵画における色彩の優位の強調ということになろう。ただ、スプレマチズムの実践からすれば、第一義的なのは基本的な「煉瓦」への絵画の分解ではなかろうかとも考えたくなる。こうした三種類の解釈は互いに矛盾するものではない。スプレマチズムの実験は、色彩が優位を占めていること、そして基本的諸形態が絵画の第一義的構成要素であることを主張している。またそれと同時に、これはキュビスムの克服――無対象性への脱出――でもあった」(36ページ)
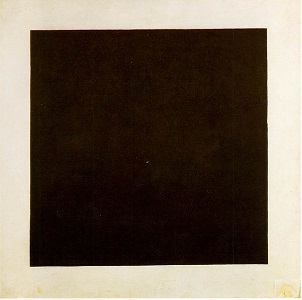
マレーヴィチ《白の上の黒い方形》(1915)
マレーヴィチ自身はスプレマチズムについて以下のように書いており、また、その後の彼の作品としては《スプレムス56》が紹介されている。
「いろいろな指導者たちが、芸術を自分たちの目的に従属させようとして、芸術は階級的差異に区別できるとか、ブルジョア的芸術、宗教的芸術、農民的芸術、プロレタリア的芸術などがある、と教えている。……現実に二つの階級の闘いが起こっており、どちらの側もそれぞれを反映し手伝う芸術をもっている。……だが新しい、無対象の芸術はいずれにも仕えず、いずれにも必要のないものである」(マレーヴィチのノートからの引用(1924年)、36~37ページ)

マレーヴィチ《スプレムス56》(1916)
抽象絵画のもうひとりの創始者として知られるカンディンスキー(ここではカンジンスキイ)は、こう書いている。
「自然現象の芸術的模倣すら目的とはみなさない画家は、自分の内面世界を表現しようとしており、またそうすべきである創始者となっている。画家には、あらゆる芸術のなかでいまや物質性とはもっとも縁のない音楽によって、こうしたことがいとも自然にかつ簡単に達成されているのが、うらやましくてたまらない。当然のことながら、画家は音楽を調べ、それとおなじような手段を自身の芸術のなかに見いだそうとしている。リズムや数学的な抽象的コンストラクションの分野における現代の探求は、ここに端を発している」(カンジンスキイからの引用、18ページ)
なにがおもしろいって、もはや話題は描かれている対象ではなく、それを観るものたちの認識の作用のほうなのだ。その抽象がもたらすものの狙いは、哲学によってのみ説明されることが可能なものである。
「理論が実際に実践に先んじたケースもあげられる。とくに、1900年からドイツで活動しており科学上の発見に高い関心をつねに示していたカンジンスキイは、1907年に出版されたヴォーリンガーの『抽象と感情移入』を無視するわけにはいかなかった。ヴォーリンガーは、ゴシック芸術の非写実的な形態をルネサンスの自然主義と対照させ、人間の意識にとって抽象化がもつ意味を問題にし、「抽象への傾向は、世界を前にした人間の大きな不安の結果であり、かれらは、認識力に誇りをもちながらも、精神的に無力になっている。新たな世界地図を前にしたときの原始民族とおなじように。」と書いていた」(38ページ)
「画家(スプレマチスト、キュビスト等々)と現実とのあいだの関係は、認識する側と認識される側の弁証法的相互作用に関するマルクスの考えをほぼ文字どおりに再現している。伝統的な唯物論が知覚や認識を、認識主体に認識客体が作用するような受動的過程と見なしていたのにたいして、マルクスによれば、能動的なのは認識主体である。客体は、それを認識する過程で改変される生の素材なのである(それゆえに、認識は世界改変という目的をもっていることになる)。「ここでマルクスがいわんとしていることは、哲学者たちが知の探求と呼んでいる過程が、以前考えられていたような、客体が恒常的であるような過程ではなく、変化が認識側によって起こされる、ということではなかろうか。反対に、主体も客体も、認識される側も認識する側も、相互変化の連続的過程に加わるのである」、とバートランド・ラッセルは書いている」(40~41ページ)
デュシャンの便器に顕著なように、この考え方はロシアに限定されたものではなく、20世紀美術そのものの中心的な主題となっていく。そしてこの流れは現在でも続いている。
「古典的モデル――ベラスケスの《ラス・メニーナス》であれ、レンブラントの《夜警》であれ――のディコンストラクションは、実験的な芸術活動の中核となりうる諸要素を数多くあばきだしている。裂開はますます深いレヴェルで起こっていく可能性がある。ボイスのインスタレーションのいくつかは、一見したところ、古典的な造形システムをほうふつさせるような要素はなにひとつ含んでいない。しかしそれはあくまでも「一見したところ」でしかない。このようなインスタレーションの元祖――有名なデュシャンの便器――は、店で買ったただの便器である。こうした対象は、新たな美的状況のなかにあって、古典的な芸術的複合体のなかの一契機、つまり展示によってのみ生きられている。この場合は、(他の構成要素はすべて欠落しているために異常に肥大した)この構成要素のみが、現象を美的なものとし、芸術空間への所属を決定づけている。もちろん、これは新しい芸術空間にほかならない。「規則にそってつくられた」ものが芸術作品とみなされていた時代とはちがって、いまではこの空間そのものが、独自の規則の創造者たちによってつくりだされている」(65~66ページ)
ところで芸術運動としてのロシア・アヴァンギャルドは、自分たちの成し遂げたことの現代的意味を知ることのないまま、1920年代には終焉を迎えた。ソ連の誕生である。
「20年代半ばまでには、〈未来〉という理念のなかの生きとし生けるものが死に絶えた。18世紀のフマニストたちの夢は、不自然な工業化や、奴隷根性的心性、退化的美学を伴ったソヴィエト社会という思いもかけぬかたちで実現してしまった。アヴァンギャルドの芸術は、こうした〈新しい〉文明のコンテクスト上には場所を見いだせなかった。アヴァンギャルドの芸術は、それを育んでいた〈ユートピア〉と同様、新しい現実の原理などではなく(一般にはアヴァンギャルドはこうした原理とみなされてはいるが)、古くからの夢の終焉であり、古典的伝統のエピローグであったからである」(48ページ)
「新しい条件下で生き延びるチャンスをより多くもっている構成主義という概念が生まれたのは、この頃である。いまや国家に囲われている以上、芸術には実用的な返しが要求されていた。「芸術家たちが描いた一切を、現実を閉ざす嘘」として斥けるよう呼びかけるとともに、生活そのものを「われわれの主要な運動にとって副次的な食事用の道」とみなしていた者が、いまでは、自分の芸術の実践的応用について考えざるをえなくなった」(49ページ)
その後に代替物として登場した「社会主義リアリズム」は、かつてのスプレマチストたちを徹底的に窒息させた。チャトウィンが書いていたように、「純粋な形態と色彩からなる抽象芸術は、単なる装飾ではなく真面目な作品であれば、現実世界の限界を超え、隠れた普遍的法則の世界へ入りこもうと努めるがゆえに、世俗権力のまやかしを嘲笑う」のである。ソ連の指導者たちは抽象芸術を野放しにはせず、求められたのはもっとずっとわかりやすい、労働者と指導者たちの礼讃だった。
「造形芸術においては〈社会主義リアリズム〉は、自然主義の勝利やミメーシス的形態の確立のようにみなされがちである。だが実際には、要点は、理想的主題の勝利にあり、イデオロギーに奉仕しない主題のラディカルな排除にあった」(51ページ)
「数十もの創造的個性が、三、四年のあいだに、確立された規範の枠内で活動する忠実な手工業者と化した。そのように試みたが、うまくいかなかった者もいた。「有機的に融合した」のは課題の形式的遂行で満足できるプロたちであったことは、いうまでもない。机の脚も指導者の頭もおなじように巧みに描けるブロツキイはそのように働いた。自己をおそらくさほど歪めずに周辺的な主題でしなやかな様式とみごとな造形性を保ちえた、様式の達人デイネカも、そのように働いた。ゲラシモフやヨガンソンのように公然と注文を果たす者もいた。残りの者たちは、手仕事を創作から区別することができず、空虚な人生を運命づけられた。ひときわ才能豊かな創造的個性(昨日のスプレマチスト、立体未来主義者、ネオ・プリミティヴィスト)は、生き延びようとして、「皆とおなじようになろう」と試みた」(53ページ)
だが、ソ連の支配下においてもマレーヴィチは死んだわけではない。だが彼の作品の陰鬱さはなんということだろう。こうした驚くべき変貌は、体制下の抑圧を饒舌に物語っているように思えるのだが、「指導者」と呼ばれた人たちはなにも感じ取らなかったのだろうか。
「ペトロフ=ヴォトキンの《新居。労働ペトログラード》(1937)が(全体的にこの画家の作品に固有のものではなく、なにか弱々しいにもかかわらず)、かれの創作の一般的キャンヴァスのなかになんとか調和しているのにたいして、30年代のマレーヴィチの自然主義的作品には気が滅入ってしまう。有能で、ときには天才的ですらもあり、自分の仕事に狂信的なまでに献身的な人びとのこうした驚くべき変容ぶり、突然の道徳的崩壊を説明できるものは、なにもない。大量転向、創造的個性の去勢、外的な力への意志や知性の無条件従属は、十分に組織された暴力(全体主義的文化の〈メガマシーン〉)によっても説明はつかないし、独特の大規模なパラノイアによっても、説明がつかない」(54ページ)

マレーヴィチ《クリューンの肖像》(1933)
ロシア・アヴァンギャルドの流れがソ連によって絶たれた後は、芸術創造の舞台はアメリカへと移る。だがこの本の著者ミリマノフによれば、ロシア・アヴァンギャルドとは古典的伝統のエピローグであり、その結末はすでに1915年にマレーヴィチが予告したとおりのものだった。
「ヨーロッパでも第二次世界大戦期の芸術創造は完全に麻痺させられていたわけではなかったものの、芸術の運命をになうような出来事となると、この時期はアメリカで生じていた。戦争の雰囲気がヨーロッパほど窒息的でなかったアメリカでは、種々の潮流(つまるところ、その時代)を代表する画家たちが移り住んできたこともあって、アヴァンギャルドが敷いた進路上に発展した造形伝統が――その終焉はすでに1915年にマレーヴィチの《白の上の黒い方形》が告げていた――戦後期に完結を見た」(63ページ)
「〈存在〉にたいするおののきを知らぬ今日の態度、功利主義的なものと芸術的なもののあいだ、現実とテクストのあいだの境界の決壊、芸術におけるほんものらしさの基準としての新奇さなどが証明しているように、神話的――さらに広くは形而上学的――原理、個々の文化や文化それ自体の原理が、根本的に変化しつつある。その存在史上はじめて、芸術――調和の源泉――は混沌の生成器となりつつある」(68ページ)
現代の美術については、わたしはなにも語ることはできないが、それが資本主義と密接に関わっていることは想像がつく。アンディー・ウォーホルの名を挙げるまでもなく、人目に付くことを許された一部の芸術作品というのは、資本主義的な市場の論理と無縁ではない。やがて社会主義リアリズムが彼らを窒息させることなど知る由もなく、ロシア・アヴァンギャルドの芸術家たちの作品は、当時革命の支持者として街に飛び出していた。ミリマノフによるこの関連の指摘はまことに興味深いと思う。
「芸術的創造とその所産がすぐれた商品となってきているときには、世界市場への登場は生き残りの条件である。この場合、単純な模倣もなしではすませられない。要求される(世界的)レヴェルに達するには、新参者は、とてつもない距離を克服しなければならない」(70ページ)
「1917年の革命の翌日には芸術(絵画、横断幕、舞台模型、彫刻)は街頭にあらわれた。今日もまた芸術は街頭へとはねでている、ただし今度は「貨幣制度の」商品として」(「注」より、86ページ)
まったくの門外漢であるわたしのような人間が入門書として手に取るには、いささか難解にすぎるようにも思えたが、結果的にはすばらしい満足感とともに本を閉じた。訳文の調子や構成、不要に思える「訳者あとがき」に文句を付けたい気持ちはあるが、本文自体はそれらのことに目をつぶらせるに十分な魅力を持っている。じつにたくさんのことを教えてくれる一冊だった。
〈読みたくなった本〉
Louis-Marie Lécharny, L'art pompier
ヴォーリンガー『抽象と感情移入』

抽象と感情移入―東洋芸術と西洋芸術 (岩波文庫 青 650-1)
- 作者: ヴォリンゲル,草薙正夫
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1953/09/05
- メディア: 文庫
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
バートランド・ラッセル『西洋哲学史』

西洋哲学史 1―古代より現代に至る政治的・社会的諸条件との関連における哲学史 (1)
- 作者: バートランド・ラッセル,市井三郎
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1970/03/30
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (14件) を見る

西洋哲学史 2―古代より現代に至る政治的・社会的諸条件との関連における哲学史 (2)中世哲学
- 作者: バートランド・ラッセル,市井三郎
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1970/03/30
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 5回
- この商品を含むブログ (6件) を見る

西洋哲学史 3―古代より現代に至る政治的・社会的諸条件との関連にお 近代哲学
- 作者: バートランド・ラッセル,市井三郎
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 2000
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
アーサー・ケストラー『真昼の暗黒』
「いうまでもなく、「鼓舞する」思想は、どんなものであれ、ある程度押しつけ的性格をおびている。思想は、ひとたび「大衆をとらえる」と、その潜在力を何倍にも増していく。しかも、「とりこにされなかった者たち」の物理的除去が、(恐怖その他をとおして)「押しつけ度」の高まりをもたらす(こんなふうにすべては循環している)。しかし、「定言命法」をどう考えればいいのであろうか。「人間を殺せてもその心をつかむことはできない」ということをどう考えればいいのであろうか。あるいはまた、殉教者や英雄の全人類的パンテオンを。たしかに、ケストラーの説明はあるものの(小説『真昼の暗黒』を参照)、かれが問題にしているのは「とりこにされた者たち」の悲劇である。この小説では、専横の犠牲になった人びとの悲劇が説得力豊かに描かれているが、このイギリスの作家は、党自体が向けた抑圧にたいして無力感をいだき失望した忠実な党員たちを描いている」(「注」より、82ページ)

- 作者: アーサーケストラー,Arthur Koestler,中島賢二
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2009/08/18
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 8回
- この商品を含むブログ (20件) を見る
ジャン=フランソワ・リオタール『こどもたちに語るポストモダン』
「リオタールは「ポストモダンとはいかなるものであるか」という問いに答えながら、つぎのように書いている。「ポストモダンの芸術家や作家は、哲学者としての立場に立たされている。かれらが創造するテクストや作品は、すでに存在する規則によって支配されておらず、それらは存在するカテゴリーにもとづいては評価できない。これらの規則やカテゴリーこそ、その作品あるいはテクストが探し求めているものなのだ。したがって、芸術家や作家は、規則をもたないまま、これからなしとげられるであろうものの諸規則を確立するために、仕事をするわけだ」」(「注」より、85ページ)

- 作者: ジャン=フランソワリオタール,Jean‐Fran〓@7AB7@cois Lyotard,管啓次郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1998/08
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 48回
- この商品を含むブログ (25件) を見る
